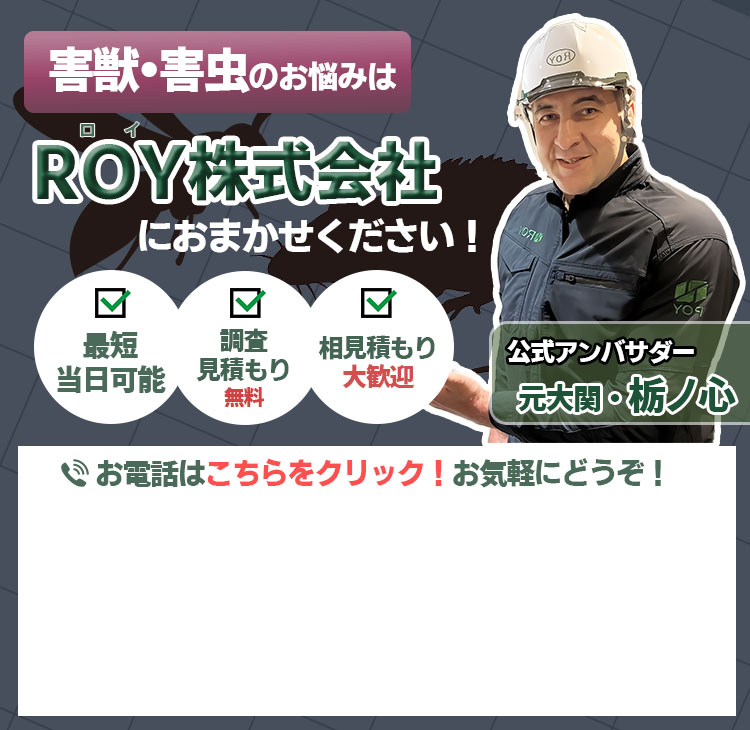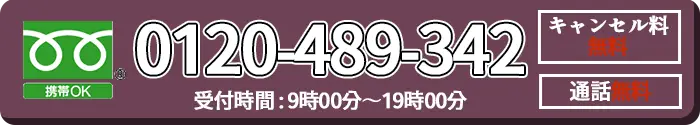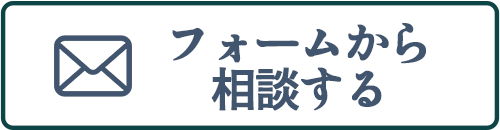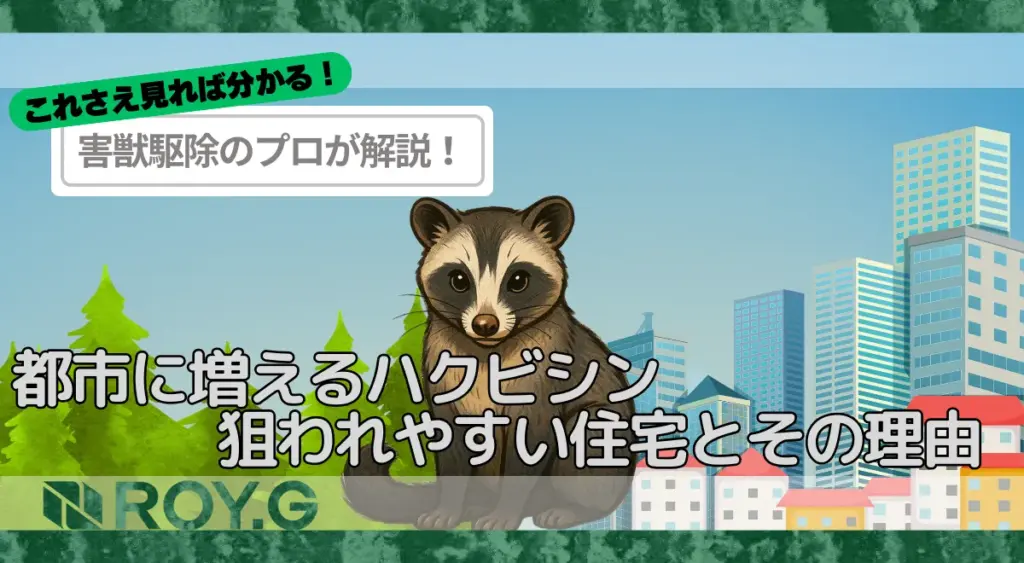
近年タヌキやイタチにも似たあの動物が都市部の住宅地でも増えてきました。
なにかご存知ですか・・・? その正体“ハクビシン”です。
ハクビシンは、可愛らしい見た目とは裏腹に、住宅への侵入や農作物被害、さらにはフンによる悪臭など、人間の生活にさまざまな影響を及ぼす存在です。なぜ、こうした野生動物が都会にまで出没するようになったのでしょうか?
この記事では、都市へと住まいの拠点を変えた彼らの行動の背景と生態系の変化を掘り下げて解説していきます。
ハクビシンってどんな見た目?
まずはハクビシンの基本情報を見ていきましょう。
ハクビシンはジャコウネコ科に属する哺乳類で、顔の中央に白い線(白鼻線:はくびせん)があるのが最大の特徴です。名前の由来にもなっているこの白い線は、眉間から鼻にかけてスーッと通っており、遠目でも見分けやすい特徴です。
東南アジア原産ともいわれ、日本では「外来種」とされる説と、「江戸時代以前から存在していた在来説」があり、定説は分かれています。

体長:約50~75cm(※尾を含めると1m以上に達する個体も)
体重:3~5kg前後(猫よりやや細長い印象)
習性:夜行性・雑食性・樹上生活を好む(木登りが得意)
生息地:山林~都市部まで幅広く適応

・白鼻線(はくびせん)
・丸みのある顔つき
・鼻が大きめでピンク〜黒っぽい
・耳が丸くて毛に埋もれ気味
なぜ都市部で目撃されるのか
① 森林破壊と人間活動の拡大による生息地の喪失
近年、宅地開発・ゴルフ場建設・高速道路整備などにより、ハクビシン本来の生息地である森林や雑木林は急速に減少しています。特に郊外エリアではかつての緑地が住宅街に変わり、ハクビシンにとっての「食べる・隠れる・繁殖する」場が失われつつあります。
こうした環境の変化は、彼らにとって“生きるための選択”を迫る要因となり、結果として都市部への移動・定着が進むようになりました。
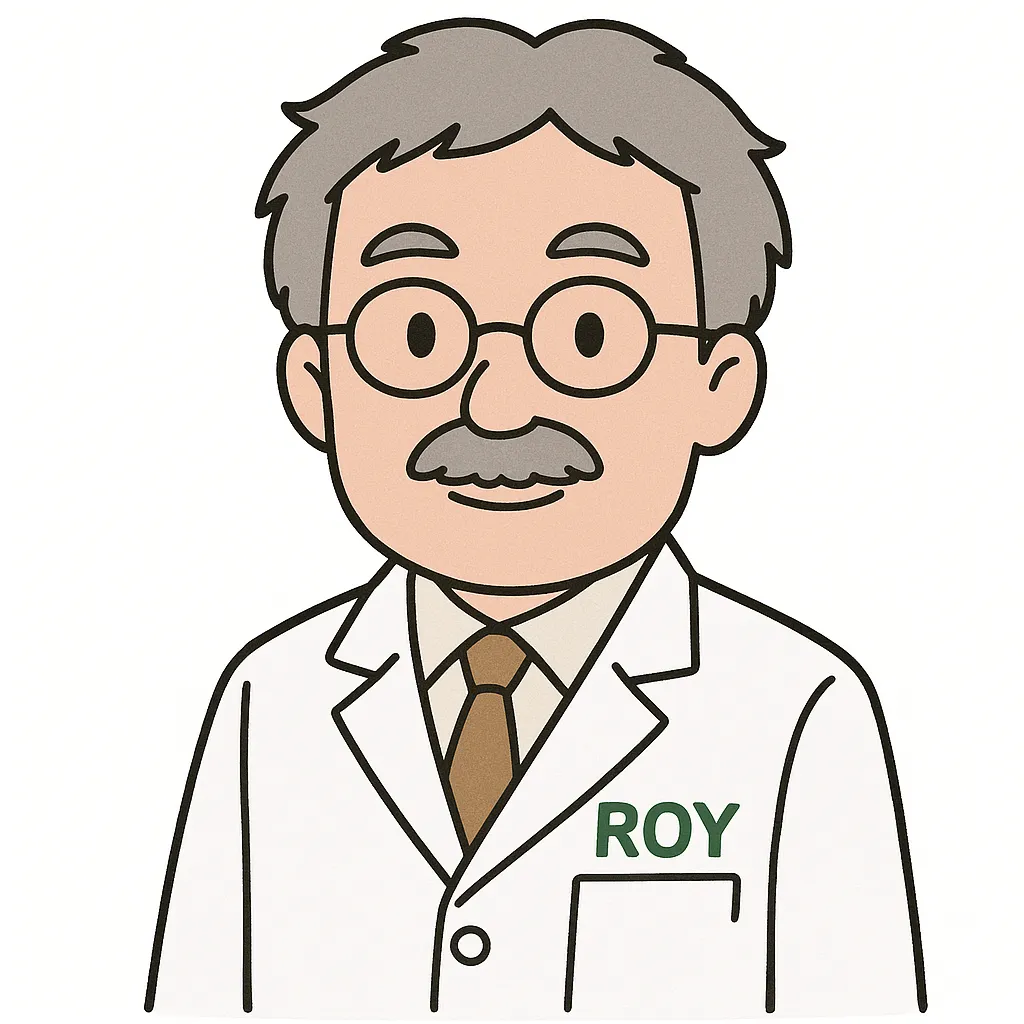
住みかを奪われたハクビシンは、都市に“避難”してきたのです。
② 驚異的な「適応力」:都市生活へのシフト
ハクビシンは非常に柔軟で順応性の高い動物です。自然界では木の上や洞穴をすみかとしていましたが、都市部ではその代わりに屋根裏・軒下・ビルの植え込み・倉庫の隅などをねぐらとして利用するようになっています。
また、人間社会にある人工物(電柱・フェンス・雨樋)を器用に活用して移動する様子からも、都市構造に対する驚くべき適応力が見て取れます。
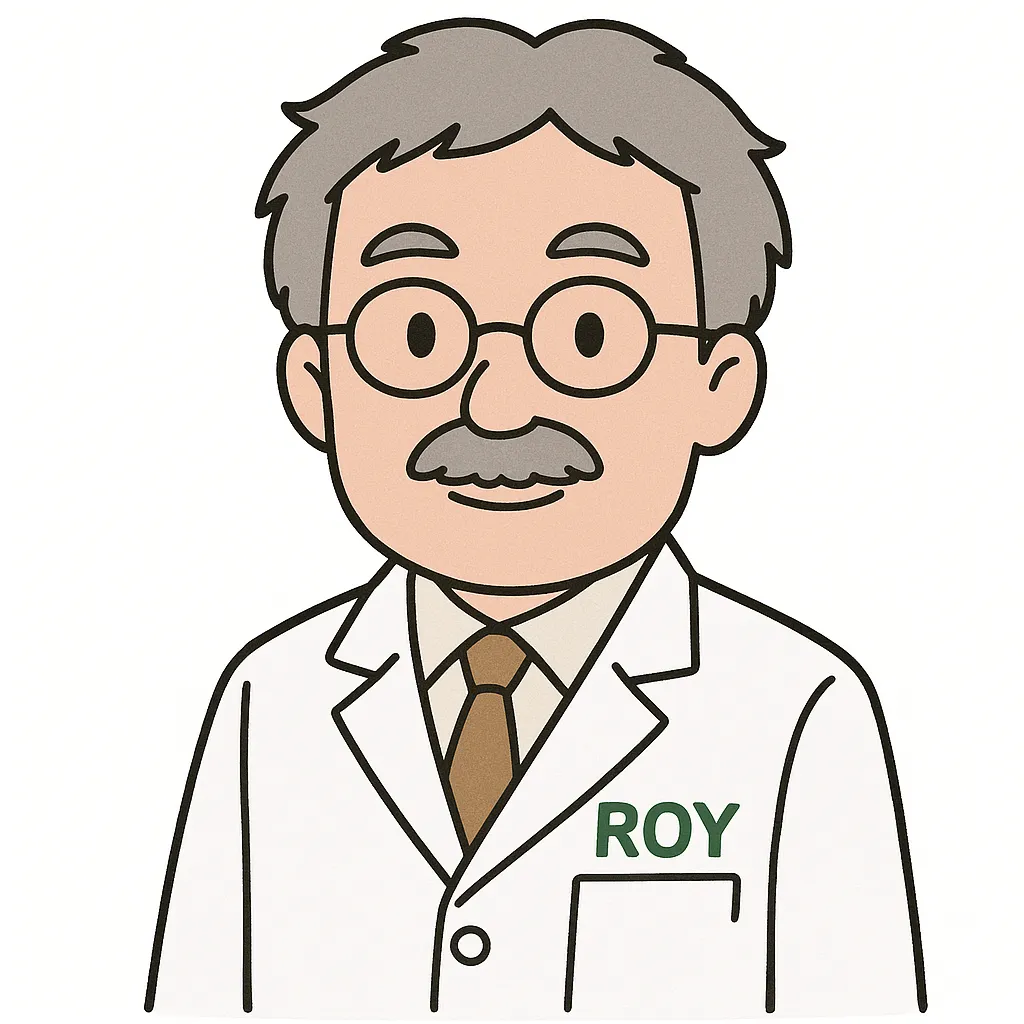
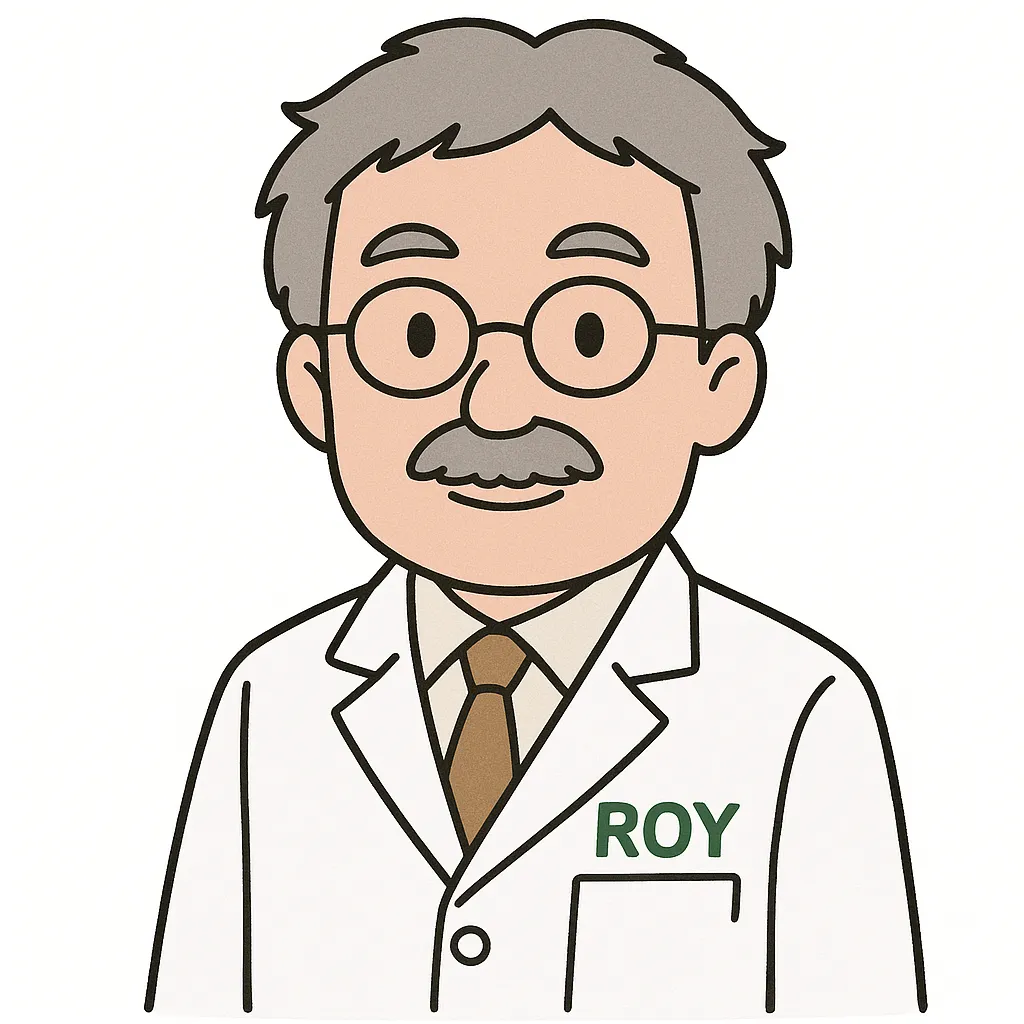
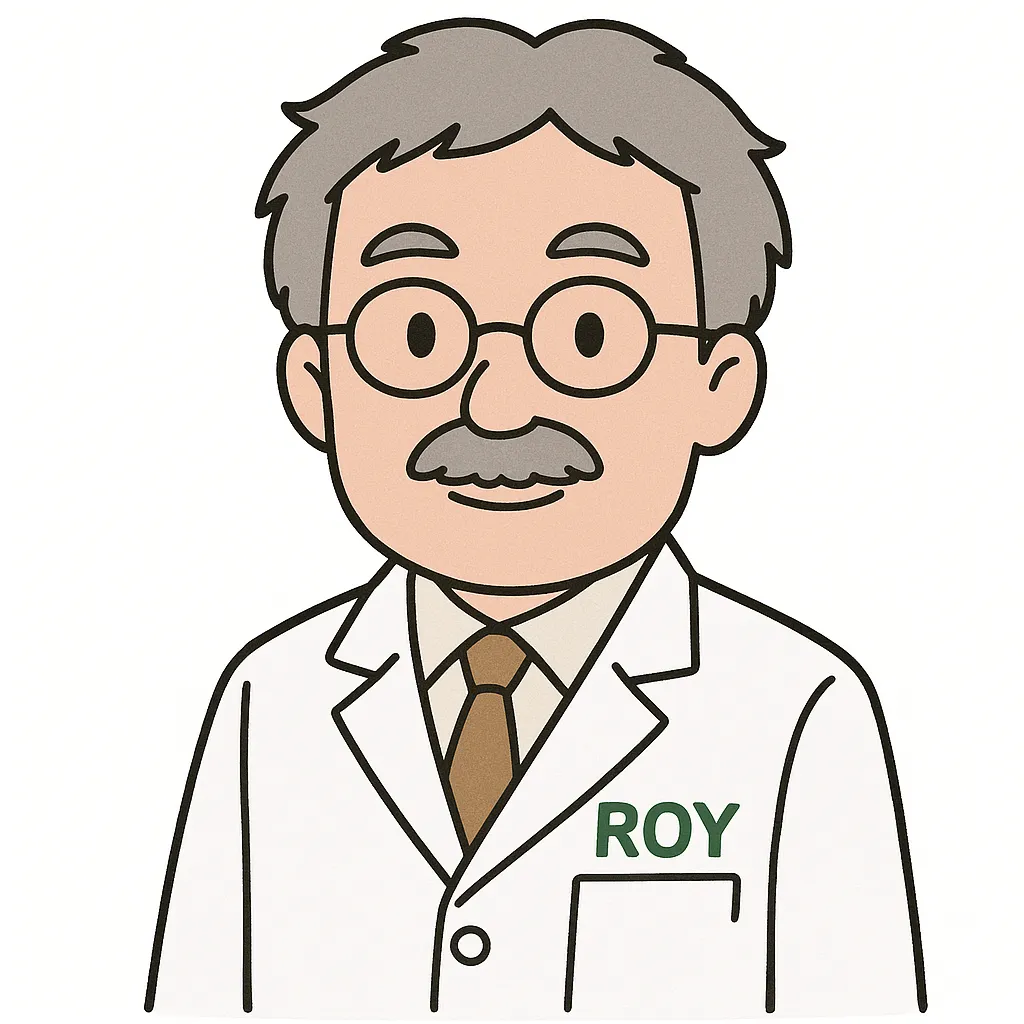
ハクビシンは“都会の構造”すら味方にして生き抜いています。
③ 都市部の「エサの豊富さ」が最大の魅力に
都市はハクビシンにとって“宝の山”です。家庭ゴミ、生ゴミ、ペットフード、熟した庭の果物、家庭菜園の野菜など、人間が日常的に出すエサが豊富に存在します。しかもこれらは自然界のエサと違い、年中安定して手に入るという大きなメリットがあります。
特に、夜間にゴミが出される地域では、夜行性のハクビシンにとっては絶好の食料供給タイミングとなり、「毎晩同じルートで巡回する」習性が定着してしまうケースもあります。
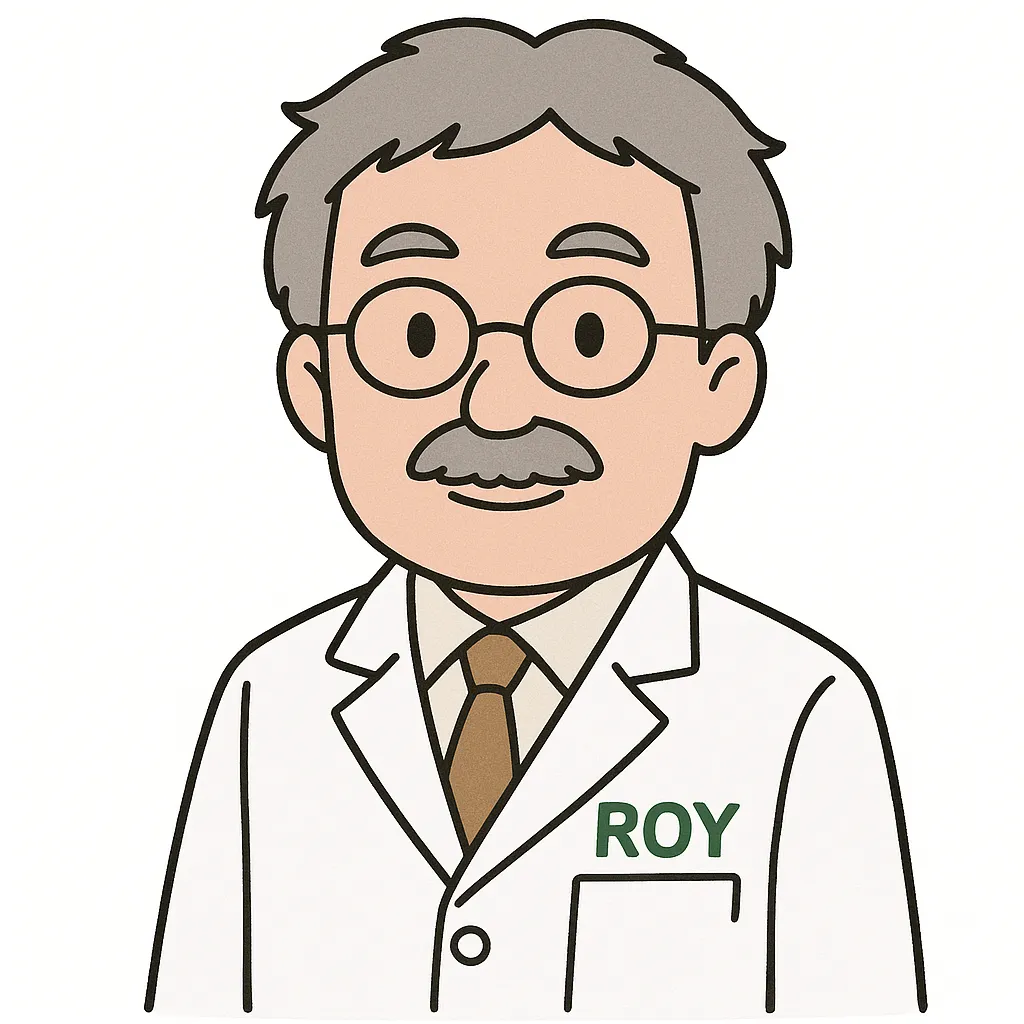
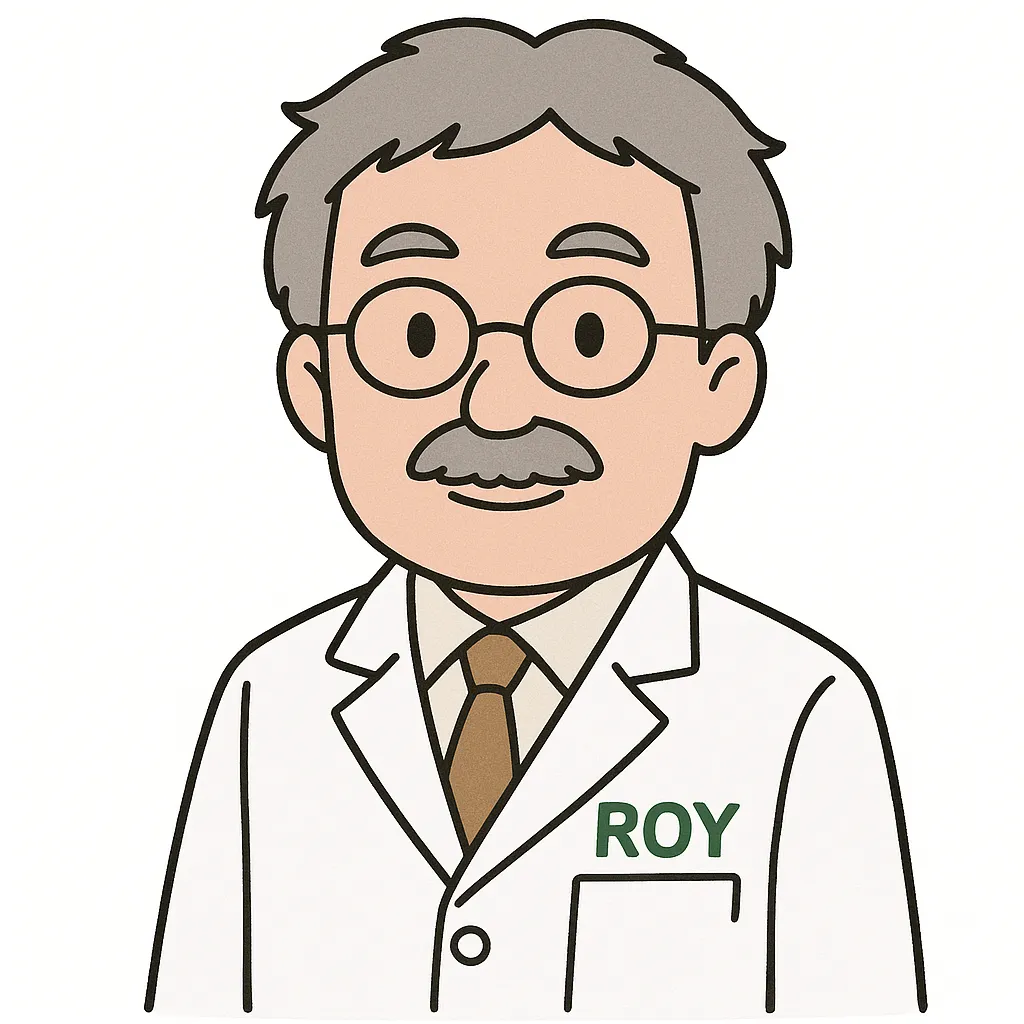
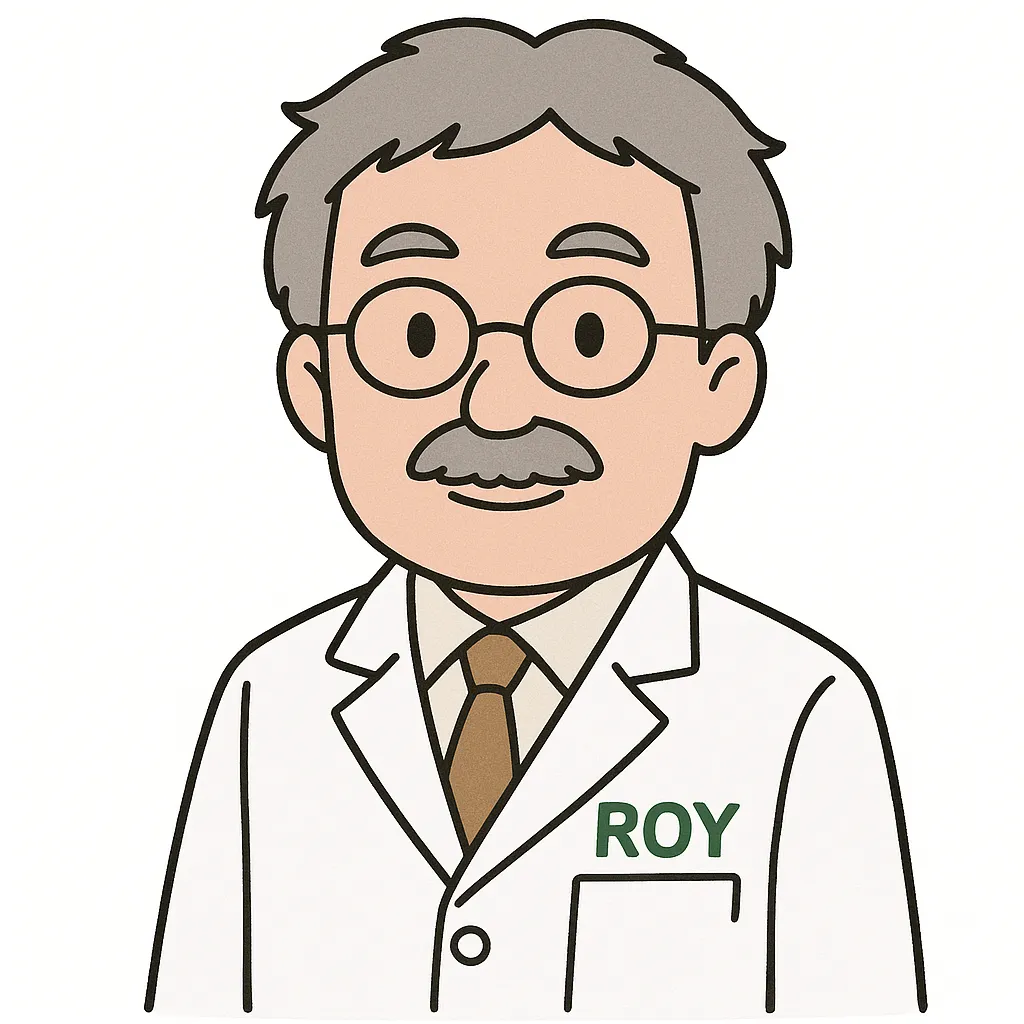
都会は、ハクビシンにとって“食べ放題のレストラン”なのです。
④ 天敵がほぼいない「安全な環境」
都市部にはハクビシンの天敵となるような大型肉食獣(オオタカ・テン・イヌワシなど)はほとんど生息していません。そのため、ハクビシンが自然界よりも長く生き、繁殖に適した環境が整ってしまっているのです。
また、都市では人の目が多くなることで、逆に大型肉食獣が寄り付かないため、ハクビシンにとっては“人間のそばこそ安全地帯”という皮肉な構図ができあがっているとも言えます。
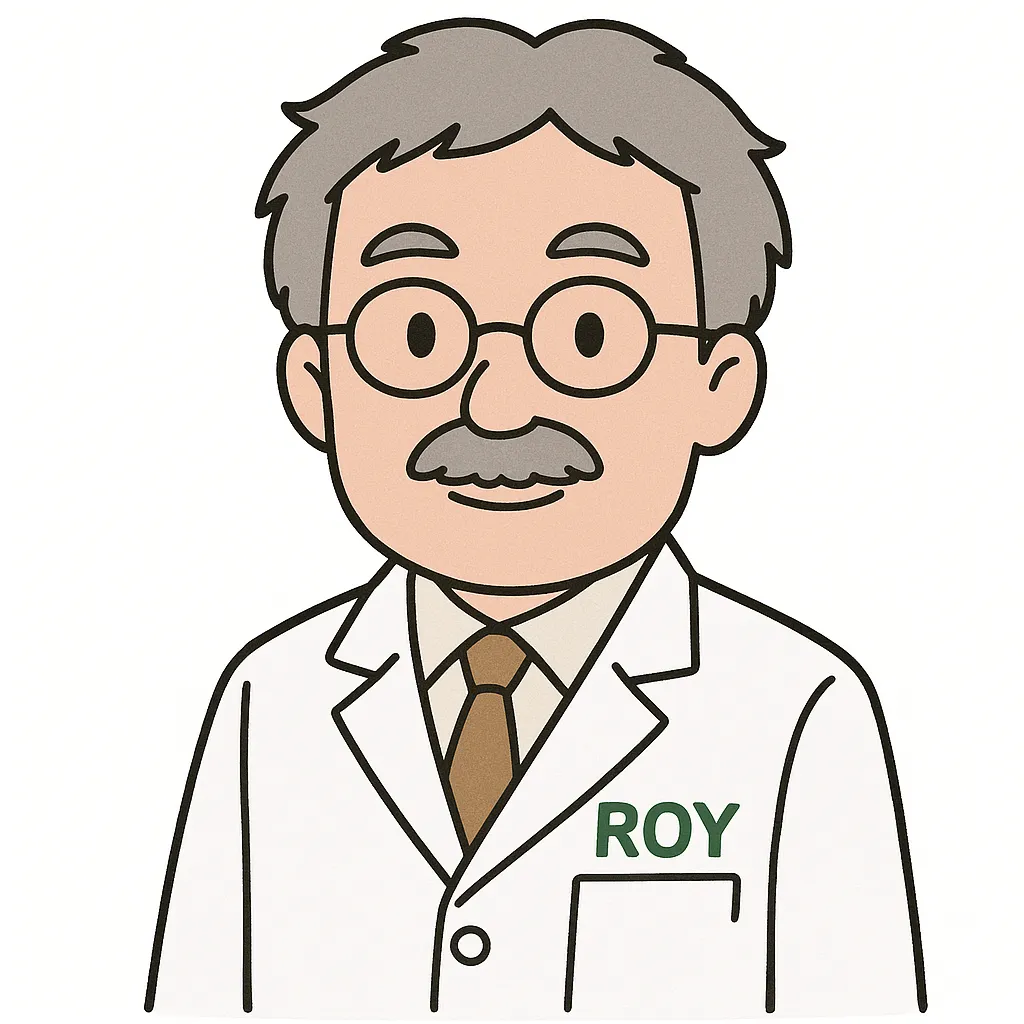
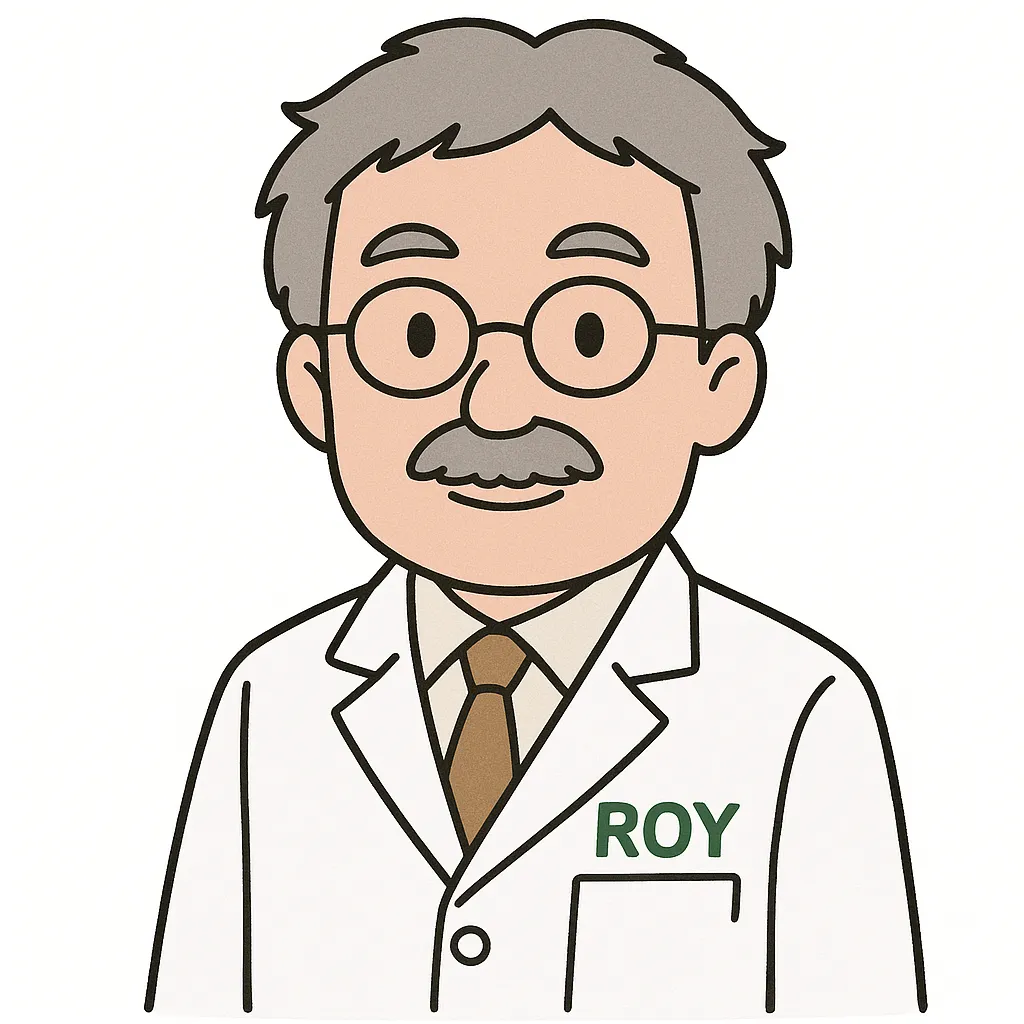
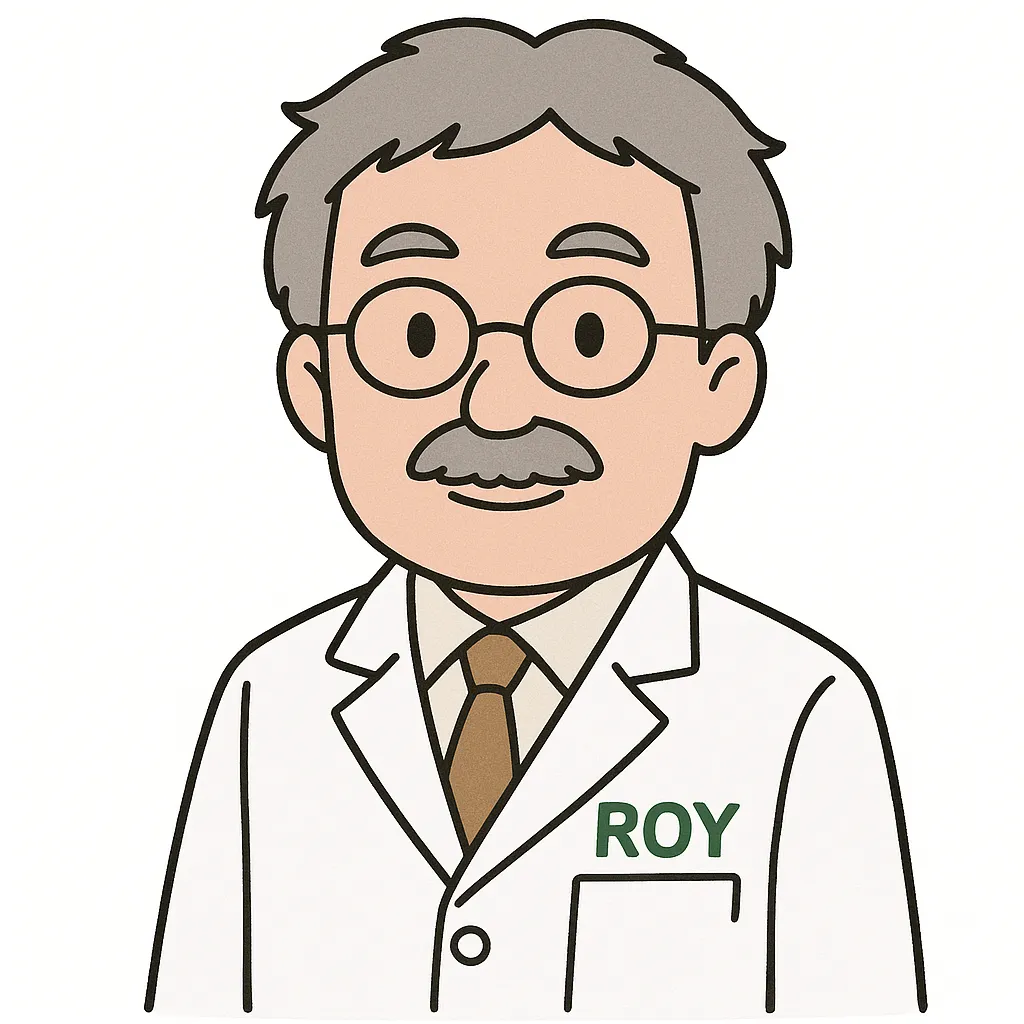
「人のそばが一番安全」これが都会に住み着くハクビシンの常識です。
ハクビシンはどんな建物でも侵入?!


ハクビシンの住まいへの侵入被害は、「音がする」「ちょっと臭う」といった小さな違和感から始まります。しかし、そのまま放置すると、住宅の構造や家族の健康にまで深刻な影響を及ぼすケースも少なくありません。以下では、具体的な被害例を項目ごとに詳しく解説します。
築年数が古い戸建住宅
瓦屋根やトタン屋根が劣化していたり、換気口や軒下にゆるみがあったりする住宅では、ハクビシンが侵入できる隙間が多く存在しています。特に、築年数の経過した家では建材の継ぎ目や通気口の金網が古くなっていることが多く、わずかな力で押し破られてしまうケースも少なくありません。
また、屋根裏の構造が広い住宅では、ハクビシンにとっては格好の巣作りスペースになります。内部の断熱材を引きちぎって巣材に利用することもあり、一度侵入を許すと、定着しやすい環境が整っているのです。
古い一軒家は“住みつくための空間”がそろっています。
隣家との隙間が狭い住宅密集地の家
瓦屋根やトタン屋根の劣化、換気口や軒下のゆるみといった箇所は、ハクビシンにとって絶好の侵入口となります。こうした隙間が多い住宅では、知らないうちに侵入されてしまうリスクが高まります。
さらに、建材の継ぎ目や通気口に設置された金網が古くなっていると、ハクビシンが簡単に押し破って内部に入り込むこともあります。
屋根裏の構造が広く空間に余裕のある住宅では、断熱材を引きちぎって巣作りに利用されやすく、ハクビシンにとって非常に住みやすい環境が整ってしまいます。
近隣住宅が被害は要注意です。
果樹や家庭菜園がある住宅
柿・いちじく・ぶどうなどの果樹や、トマト・さつまいもなどの野菜を庭や家庭菜園で育てている住宅は、ハクビシンの被害を受けやすい傾向があります。特に甘い果実の香りはハクビシンを強く引きつけ、夜間になるとエサを求めて繰り返し訪れるようになることが多いです。
一度エサ場として認識されてしまうと、その場所を「食べるだけでなく、住みつく場所」として選ぶ可能性も高まり、被害はさらに深刻化します。
庭先の“ごちそう”が、侵入のきっかけになることも。
高層マンションでも油断は禁物
「うちは高層階だから大丈夫」と思っていませんか?実は、ハクビシンは雨樋や樹木、隣接する建物から高層階へも侵入できる運動能力を持っています。10階以上でのフン害やベランダ菜園の荒らしなど、都心の高層マンションでも侵入被害の報告が増えています。
とくに夜間、人通りが少なくなる時間帯には、ハクビシンがベランダや非常階段を使って行動範囲を広げているケースも確認されています。
「マンションは安心」という常識は、今や通用しません!
店舗付き住宅・倉庫付き住宅
飲食店やスーパーなどが1階に併設されている建物では、食品残渣や生ゴミの匂いがハクビシンを引き寄せる原因になります。とくにゴミ置き場が建物の裏手にある場合、その周囲がハクビシンの巡回ルートとなることもあります。
また、倉庫や物置の扉のわずかな隙間、あるいは排気口・配管の穴などの開口部から侵入されるケースも多く、対策が不十分なままだと建物内部に住みつかれてしまう恐れもあります。
さらに、夜になると人の出入りが減ることから、夜行性のハクビシンにとっては“安心して行動できる快適な時間帯”となり、侵入や餌探しがより活発になります。
ハクビシンは人の出入りが少ない時間帯を狙って侵入してきます。
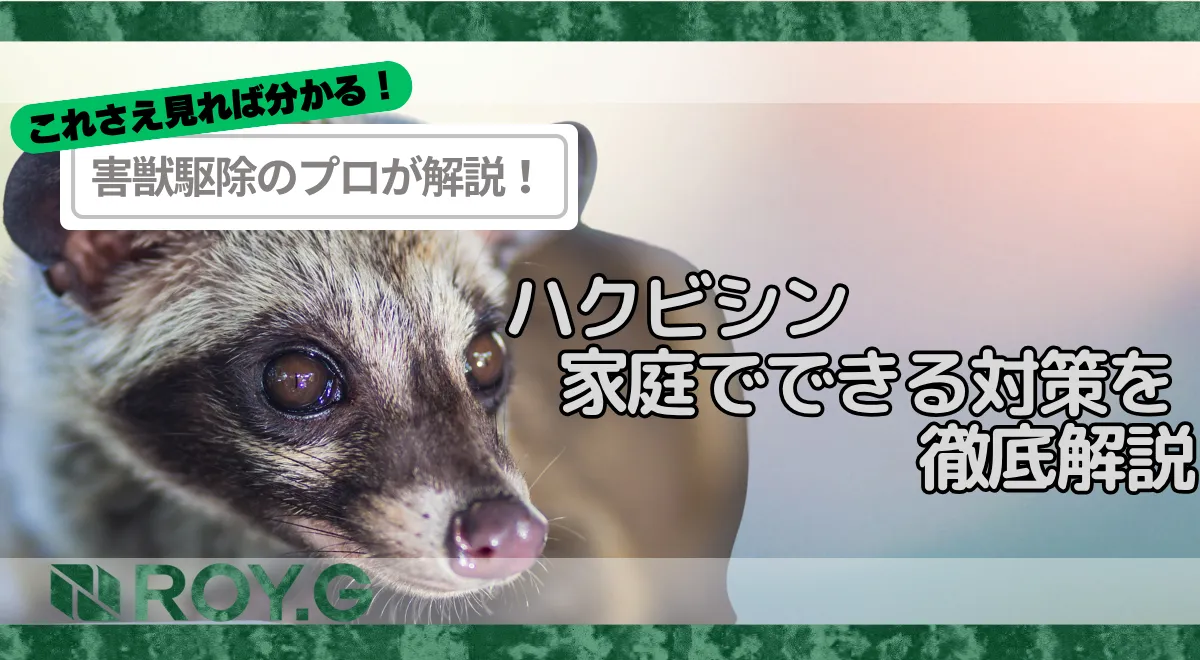
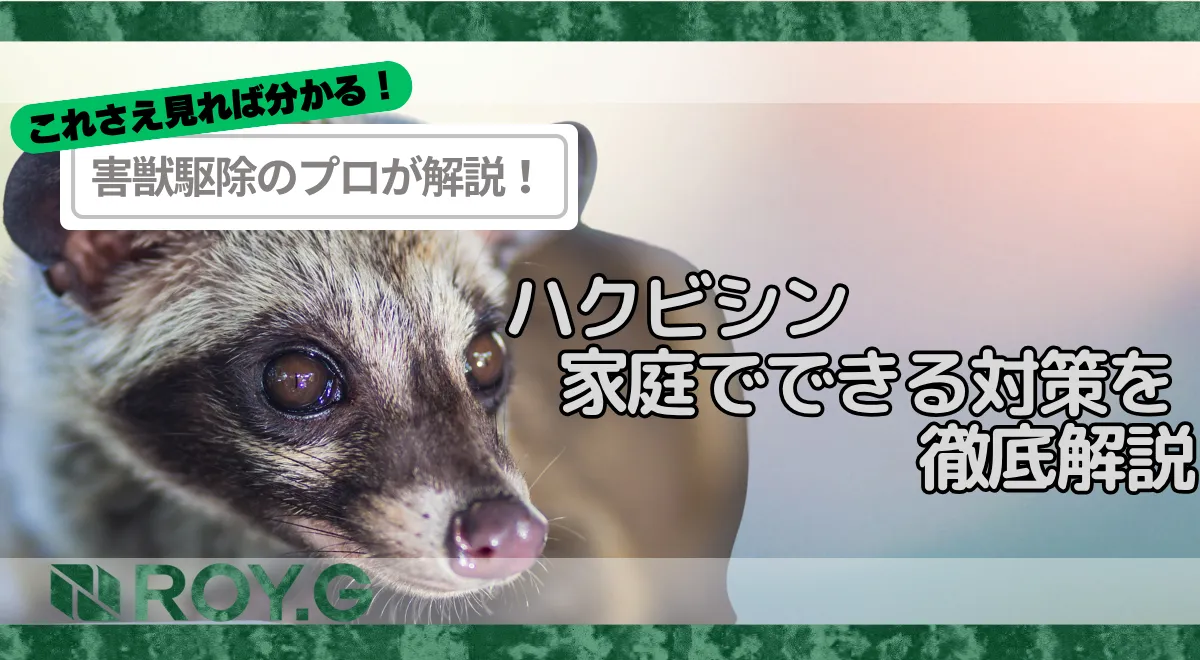
なぜ捕獲しなければならない?
住宅被害の拡大を防ぐため
ハクビシンが住みつくと、屋根裏・天井裏・床下などの住宅構造に被害が及びます。


- 断熱材を引きちぎって巣にする
- フンや尿で天井材が腐敗・変色
- 木材や壁材が湿気やカビで劣化
- 天井から悪臭が室内に染み出す
放置すれば、家屋全体の工事になるケースもあります。
健康被害・感染症のリスクがあるため
ハクビシンのフンや尿には、病原菌や寄生虫(回虫・サルモネラ菌など)が含まれている可能性があります。また、体にマダニを寄生させていることが多く、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)などの感染症の媒介源になる恐れも。
【SFTS(重症熱性血小板減少症候群)】
2011年に中国で初めて確認されたウイルス感染症で、日本では2013年に国内初の患者が報告されました。SFTSウイルス(SFTSV)は主にマダニを介して感染し、致死率は10~30%前後と高く、非常に危険な感染症です。
近年の研究により、ハクビシンがSFTSウイルスを保有している可能性があることが明らかになっており、西日本を中心に捕獲されたハクビシンの一部がSFTSV陽性であったことが報告されています。
家庭内の衛生環境を守るためにも、早期の駆除が必要です。
繁殖スピードが早く、放置すると数が増える
ハクビシンは約10ヶ月になると出産を始めます。年に1回〜2回繁殖し、1回の出産で2〜4匹程度の子を産みます。しかも、都市部ではエサやねぐらに困らず、生存率が高いため、親子で住みつくケースが急増中です。


- 一匹だけだったはずが、数ヶ月で家族ごと定着
- 屋根裏が“巣”として完全に占拠されることも
「気づいたときには手遅れ」という事態を防ぐには、早期対応が必須です。
夜間の騒音による生活被害
ハクビシンは夜行性のため、深夜〜早朝に屋根裏を走り回る足音や物音が発生します。


- ドスドスという重い足音
- 巣材を運ぶガサガサ音
- 鳴き声(シャーッという威嚇音)
「眠れない」「怖い」といった精神的ストレスにつながることもあります。
一度住みつくと、繰り返し戻ってくる
ハクビシンは自分が快適だと感じた場所に執着する性質があります。一度追い出しても、侵入口が塞がれていなければ何度でも戻ってきます。


- 同じハクビシンが何度も侵入する
- 繁殖率が高く住み着く
- 近隣の空き家などから出入りすることも
「一度追い出したから安心」は禁物。再侵入防止までが駆除です。
駆除は「早期発見・早期対処」が鉄則
ハクビシンは見た目が可愛くても、家を傷め、健康を脅かす害獣です。最初は小さな足音やフンの発見だけでも、それが深刻な被害の始まりかもしれません。
「そのうち出ていくだろう」と放置してしまうと、家の中に巣を作られ、繁殖し、被害はどんどん広がっていきます。
だからこそ
違和感に気づいた“そのとき”が対策のタイミングです。



足音・フン・臭いを感じたら「まずは専門業者に相談すること」が何よりの早道です。
プロの判断と適切な施工で皆さまの住まい安心を守りましょう。


こんな事も報告されてます!
近年、テレビのニュース番組でも取り上げられることが増えてきたハクビシンによる都市型被害。とはいえ、ネズミやイタチに比べるとまだまだ認知度は低く、「まさか自分の家が…」という声も少なくありません。ここでは、東京都内・大阪市内で実際にご依頼いただいた戸建て住宅とマンションそれぞれのケースをご紹介します。
ー戸建て住宅(天王寺区)ー
屋根の隙間から侵入、屋根裏に巣を作られていた
築30年の木造住宅にお住まいのご家族から「最近、夜になると天井からドスドス音がする」というご相談を受け、現地調査を実施。調査の結果、屋根の隙間からハクビシンが侵入し、屋根裏に巣を作っていたことが判明しました。
侵入口は瓦のズレと軒下のゆるみから、ハクビシンが通行できるスペースができていた状態。
また、フンの堆積も見られ、断熱材が一部引き裂かれていたため、追い出し作業と除菌消臭、再侵入防止の金網施工を実施。現在は無料の定期点検を継続中です。


お客様からの声
まさかハクビシンだとは思いませんでした。音はしていたけど、てっきりネズミだと…。工事の内容も的確で安心できましたし、定期点検も無料でやってくれて助かっています。
ーマンション(中野区)ー
ハクビシンをゴミ置き場と外階段で目撃
こちらは都内の分譲マンションで、ご依頼の1週間前に居住者がゴミ置き場でハクビシンらしき動物を目撃。さらに数日後、夜間に外階段を登る姿が確認され、管理人様より「今後の侵入を防ぎたい」とのご相談をいただきました。
現地調査の結果、周囲の植え込みと外階段の構造がハクビシンの移動に適していることが判明。ベランダや非常階段下などの危険箇所を洗い出し、防獣ネットと忌避剤による対策を実施しました。
管理人さまからの声
テレビで見たことはあったけれど、まさかうちのマンションに来るとは思いませんでした。住民への直接的な被害が出る前に対応してもらえて安心でした。
このように近年では東京都内・大阪市内・福岡市などの都市中心部での報告が増えています。
「高層階=安全」という油断が被害の引き金になり、「都会=安心」はもはや通用しない時代になっています。
少しでも身の回りで異変が起こったら以下の手順でお問い合わせください!
専門業者への依頼方法
【戸建て住宅の場合】
所有者の判断で、被害に気づいた時点ですぐに駆除業者へ相談・依頼が可能。
「天井裏から物音がする」「屋根に隙間を見つけた」など、どんな些細なことでも構いません。
専門業者に連絡しStep1の異変を相談、無料点検や調査の日程を決定しましょう。
侵入口や被害状況の報告を受け、必要な対策工事の説明と費用の案内を受けます。
依頼内容に基づいて実施されます。再発防止のための点検サービス付きの業者を選ぶと安心です。
再発リスクが高い住宅構造や周辺環境に応じて点検を実施することで、被害の再燃を未然に防ぎます。
【マンション・集合住宅の場合】
共用部での発生が多く、管理会社・管理組合への報告が基本。
ゴミ置き場での目撃、フンや破損箇所の発見などを写真や動画で記録しましょう。
住人からの個別依頼ではなく、建物全体の問題として共有しましょう。
Step1での被害を専門業者へお伝えください。無料点検や調査の日程を決定しましょう。
侵入口や被害状況の報告を受け、必要な対策工事の説明と費用の案内を受けます。
マンション・集合住宅では小さな見逃しが居住者への大きな被害に発展するため、点検を行いましょう。
ハクビシン被害は一度追い出しても、侵入経路の劣化や新たな隙間の発生で再侵入が起きるケースは少なくありません。
だからこそ、施工後もプロによる定期点検を実施することが、被害ゼロを維持するための確実な方法です。
ROY株式会社では、施工後の無料定期点検を実施しており、大切なお住まいそして皆様の安心が長く続きます。
ROY株式会社の対応エリアと特徴


- 対応エリア:全国対応可能
- サービス内容:シロアリなどの害虫駆除・害獣駆除・屋根雨漏り・床下などの総合リフォーム
- 戸建て専門
- 即日対応可能
- 調査・見積り無料+施工後報告書付き
- 修繕・リフォームは月々3,300円から〜
- 害獣駆除費用は4,730円から〜
よくあるQ&A
- ハクビシンは人に害を与えるのですか?
-
はい。
フンや尿には病原菌や寄生虫が含まれており、アレルギーや感染症を引き起こすリスクがあります。また、家屋の断熱材や天井板を破損するなど、構造被害も深刻です。 - ハクビシンがいるかどうか確認できますか?
-
できます。
フンや尿の臭い、天井にシミ、屋根周辺の足跡や爪痕などが確認ポイントです。ペットが天井を気にして吠える行動もサインのひとつです。 - ハクビシンは自分で捕獲していいですか?
-
いいえ。
ハクビシンは「鳥獣保護法」で保護されているため、無許可での捕獲・駆除は禁止されています。追い出しや封鎖の際は、専門業者に相談することをおすすめします。 - 高層マンションやビルなら安心ですか?
-
実はそうではありません。
2階建て程度なら雨樋や電線を伝って登ってきます、飲食店やゴミ置き場が併設された建物は特に注意が必要です。 - 調査や見積もりには費用がかかりますか?
-
一切かかりません。
ROY株式会社では、現地調査・点検・お見積もりは無料で実施しています。被害状況を確認した上で、最適な対策をご提案いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ前に
ご確認ください
必ずご確認をお願いします
お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。
tel:044-328-9227
mail:info@roy-g.com
携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。
・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。
・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
プライバシーポリシー
必ずご確認をお願いします
個人情報の定義
個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。
個人情報の収集・利用
弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。
1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集
2.お問い合わせ対応各種
個人情報の第三者提供
弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。
委託先の監督
弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。
個人情報の管理
弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。
情報内容の照会、修正または削除
弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。
セキュリティーについて
弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。
Googleアナリティクスについて
当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。
個人情報に関する苦情や相談の窓口
弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。
社名:ROY株式会社
住所:〒213-0012
神奈川県川崎市
高津区坂戸3-16-1
電話番号:044-328-9227
メールアドレス:info@roy-g.com
責任者名:大石 竜次