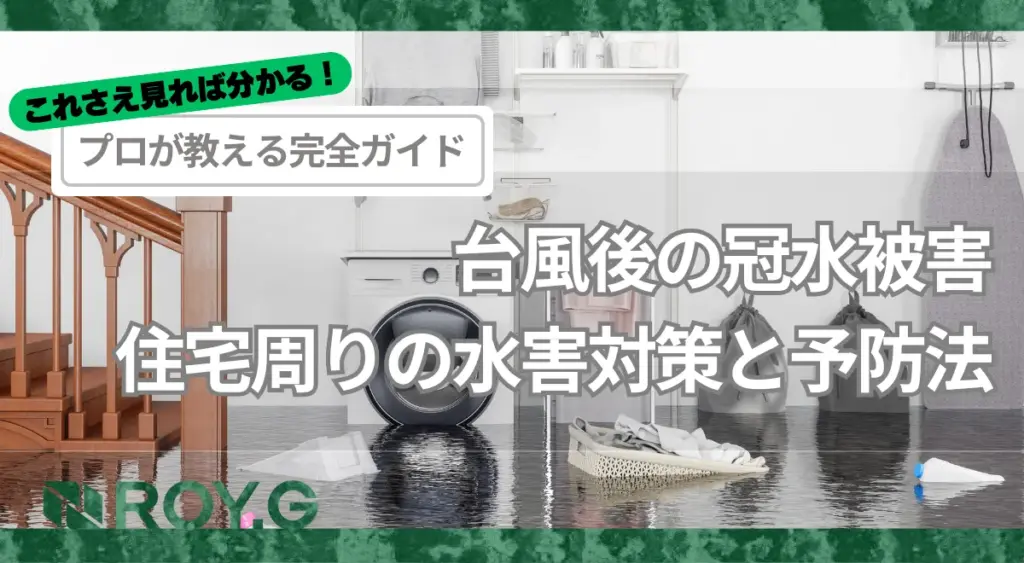
「今年は台風が多いみたいですよ」と天気予報士が言うと、なんだか落ち着かなくなる…。
そんな経験、ありませんか?
ここ数年、日本では大型台風や線状降水帯による豪雨が増え、各地で「道路が冠水した」「床上浸水した」といった被害が相次いでいます。
特に、低地や川沿いの住宅では一晩で床下に水が流れ込み、家の基礎や構造材に深刻なダメージを与えることも珍しくありません。
冠水被害は「床が濡れただけ」ではなく、住宅に甚大な被害をもたらします。
床下の木材や断熱材は水分を含むと急速に劣化し、放置すればカビやシロアリの温床に。さらに、電気設備が損傷すれば感電や火災の危険まであります。
しかし、台風での冠水の予防策や対処方法のポイントを押さえておけば、被害を最小限に抑えられるかもしれません。
本記事では、
- 冠水が起きる理由
- やっておくと良い冠水予防対策
- 緊急時の冠水対策
- 冠水後のNG行動
- 火災保険や補助金制度
などなど、わかりやすく解説します。
台風や冠水についてよく知って、不測の事態に備えられるようにしましょう。是非、ご一読ください。
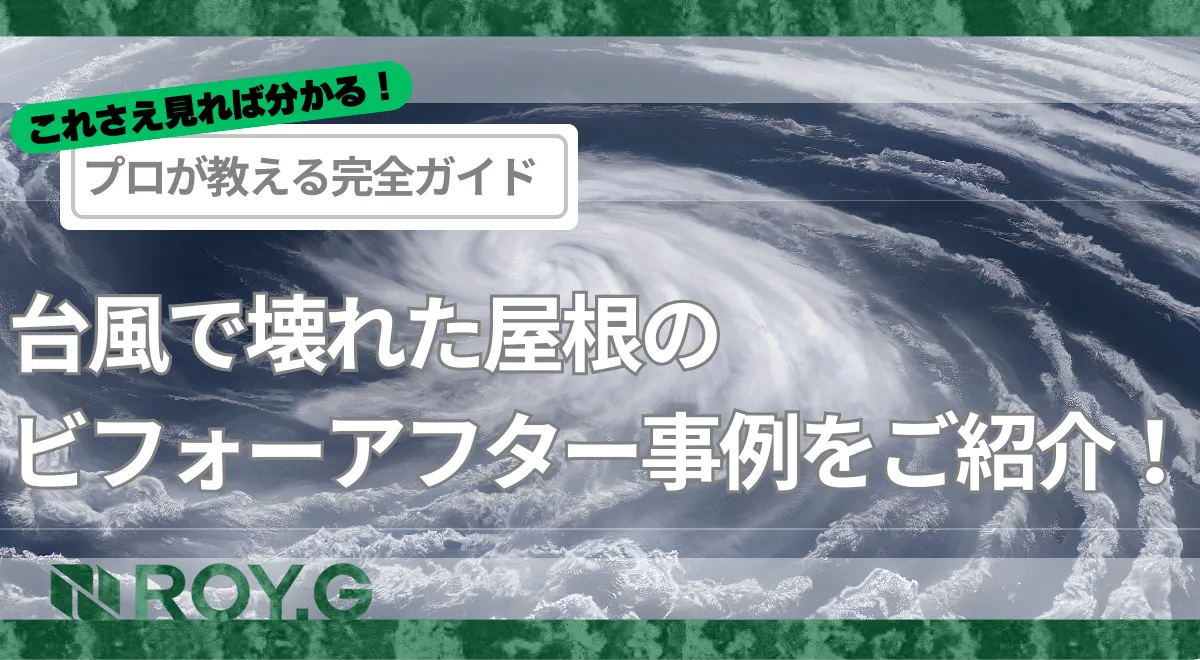
冠水はどうして起こる?

冠水はなぜ起こるのでしょうか?
ニュースやSNSで冠水している様子を見たことはあっても、どうして起こるのか、いまいちピンとこない人も多いかもしれません。
実は、冠水は「雨がたくさん降ったから」だけではなく、いくつもの条件が重なって発生します。
条件を知っておくことで、予防や対策がよりわかりやすくなるでしょう。
排水経路のつまり
台風や豪雨の前後は、激しい雨で落ち葉や泥が流れて、排水溝に溜まることも。これにより、排水溝につまりが起きて水の流れを塞ぎ、行き場を無くした雨水が道路や敷地に溢れ出してしまいます。
地形の影響
道路より敷地が低いと、雨水が自然に家の方へ流れ込みます。特に築年数の古い住宅地は、道路改修で昔より道路の高さが上がり、結果的に家が低い位置になってしまっているケースも。
河川・用水路の氾濫
近くの水路や川があふれると、下水や側溝を通じて逆流することもあります。この場合、濁水には雑菌が多く含まれており、衛生面の被害も深刻です。
やっておくと良い冠水の予防対策

台風シーズンになると、強い雨風によって住宅周辺が一気に冠水することがあります。
「もし自宅が浸水したら…」と不安な思いを抱えれている方も多いでしょう。
床下浸水や床上浸水は、住宅の基礎や家財に深刻なダメージを与えるだけでなく、衛生面や健康面にも悪影響を及ぼします。
ここではあらかじめやっておくと良い台風による冠水の予防対策を分かりやすくご紹介。日頃から予防対策をしっかりと行って、被害を最小限に抑えましょう。
排水経路のメンテナンス

家の周囲にある排水溝や雨水桝を定期的に掃除しましょう。
先ほど記載した通り、排水経路に落ち葉や泥が溜まっていると、台風時に水が流れず道路や敷地に溢れ出します。
特に台風シーズンの前に、庭や玄関前、カーポート周りの水はけを確認しておくことが大切。
排水管や枡の点検は、3〜5年に1度くらいの頻度で専門の業者に行ってもらいましょう。
 Mr.ROY
Mr.ROYROY株式会社でも排水管や枡の点検、工事まで行っております。
是非、ご相談ください!
外構・庭の排水改善


庭や駐車場の水はけが悪い場合は、暗渠(あんきょ)排水や浸透トレンチの設置を検討しましょう。
暗渠排水は、地中にパイプを埋め込み、雨水を速やかに排出する仕組み。これにより、雨が降っても庭に水が溜まりにくくなります。
浸水トレンチは、地面に掘った溝に砕石や透水管を入れ、雨水を地中へゆっくり浸透させる排水させる仕組み。
暗渠排水と浸透トレンチはどっちがいいの?
2つの違いを簡単に説明すると下記の通り。
- 暗渠排水は「水を遠くに逃がす工事」
- 浸透トレンチは「水をその場でしみ込ませる工事」
ではどちらが良いのでしょうか?
暗渠排水と浸透トレンチは、使用環境によってどちらが良いのか決まります。
- 短時間で大量の雨を処理したい・敷地外に排水先がある → 暗渠排水が◎
- 公共排水が負担限界・敷地内で自然浸透させたい → 浸透トレンチが有効◎
勾配や敷地高さの見直し
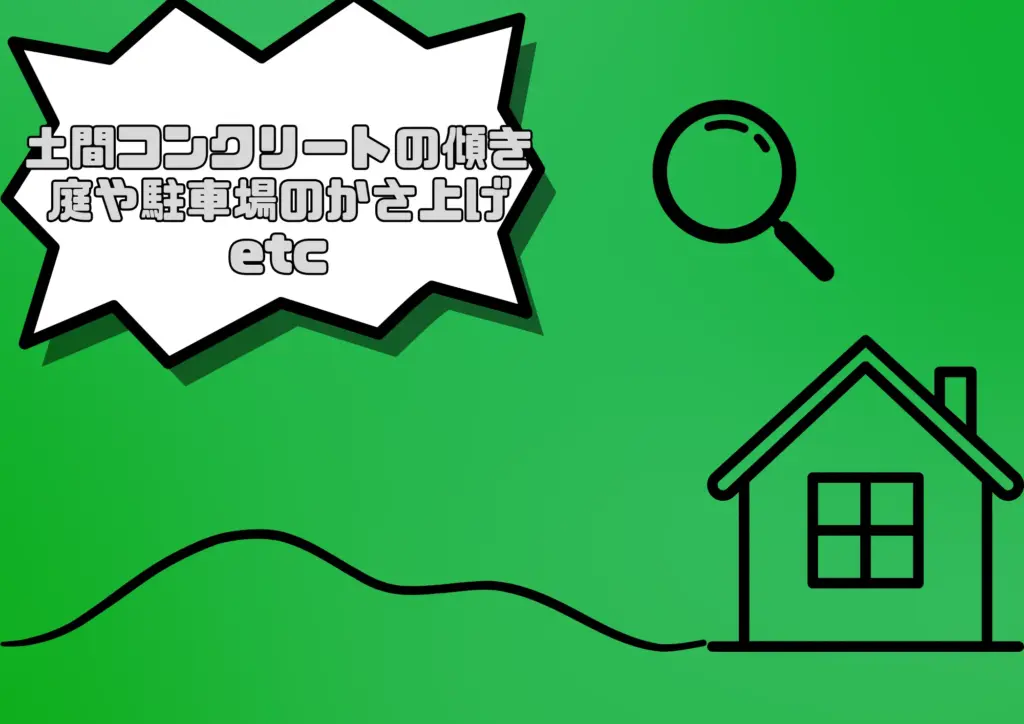
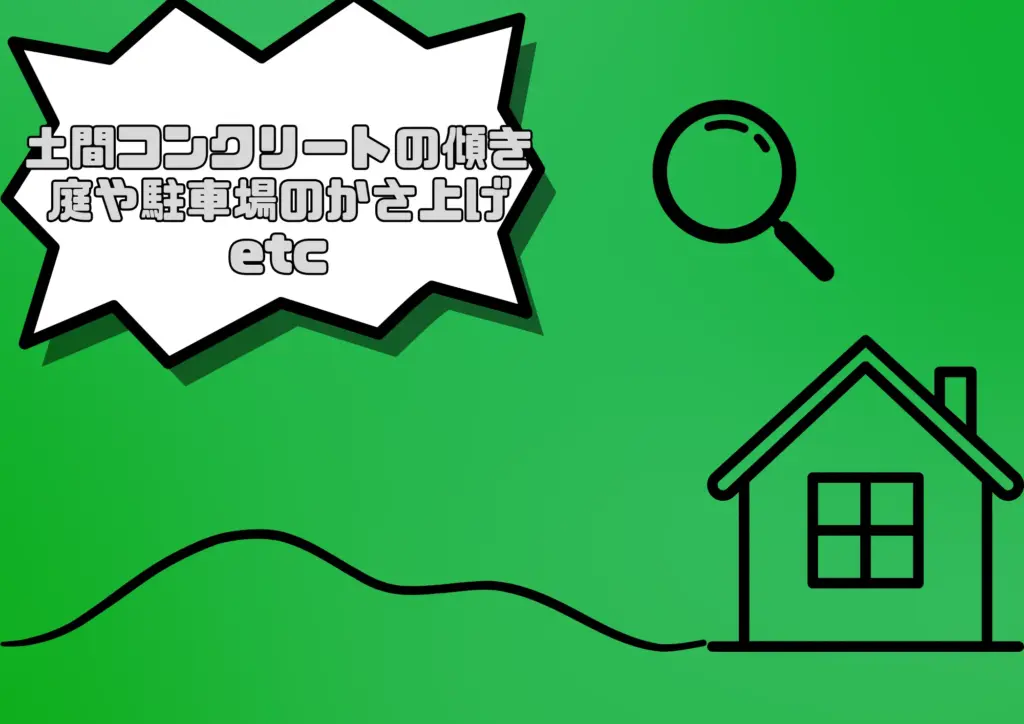
冠水が起きる原因でもご説明しましたが、住宅の敷地が道路より低いと、雨水が自然と家に流れ込んでしまいます。
そういった地形に問題がある場合、工事を行って根本的な問題を解決しておくと良いでしょう。
具体的に下記のような工事です。
- 土間コンクリートの傾きを外側へ向ける
- 庭や駐車場をかさ上げする
大掛かりな工事にはなりますが、長期的に見れば冠水の予防策として、かなり効果的です。
特に台風が多かったり、川が氾濫しやすい地域にお住まいであれば、こうした「地形の見直し」を行ってもよいかもしれません。



ROY株式会社は一級建築士にも在籍!
専門的な観点から、みなさまの住宅の見直し・リフォームを行います!
安心安全な暮らしをサポートしますので、是非ご相談ください。
火災保険と自治体支援の確認
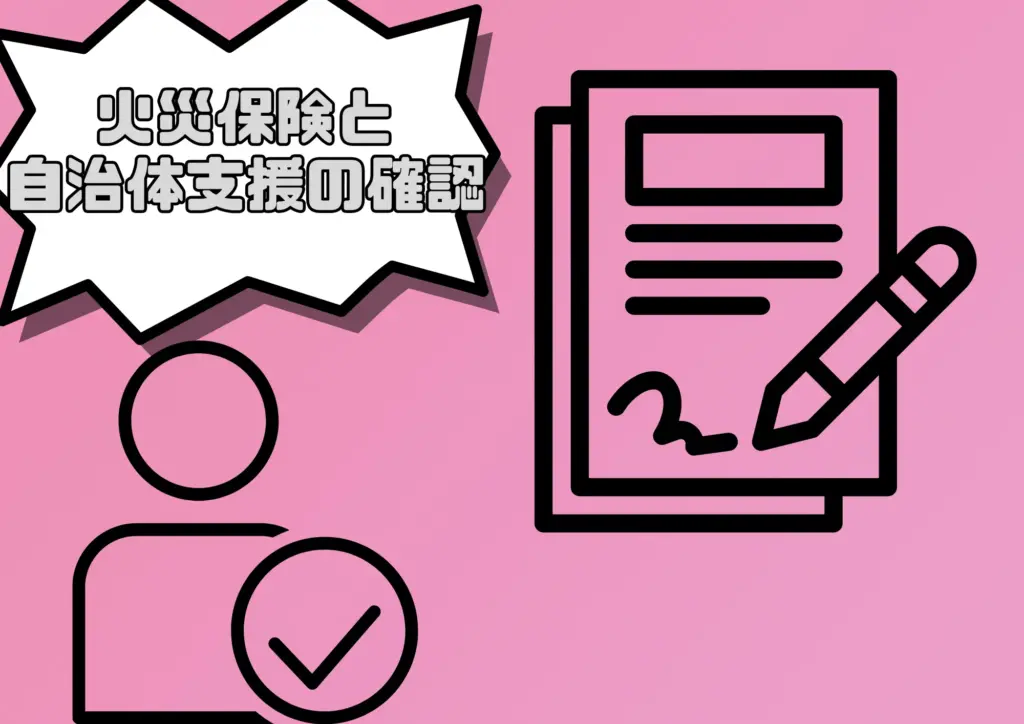
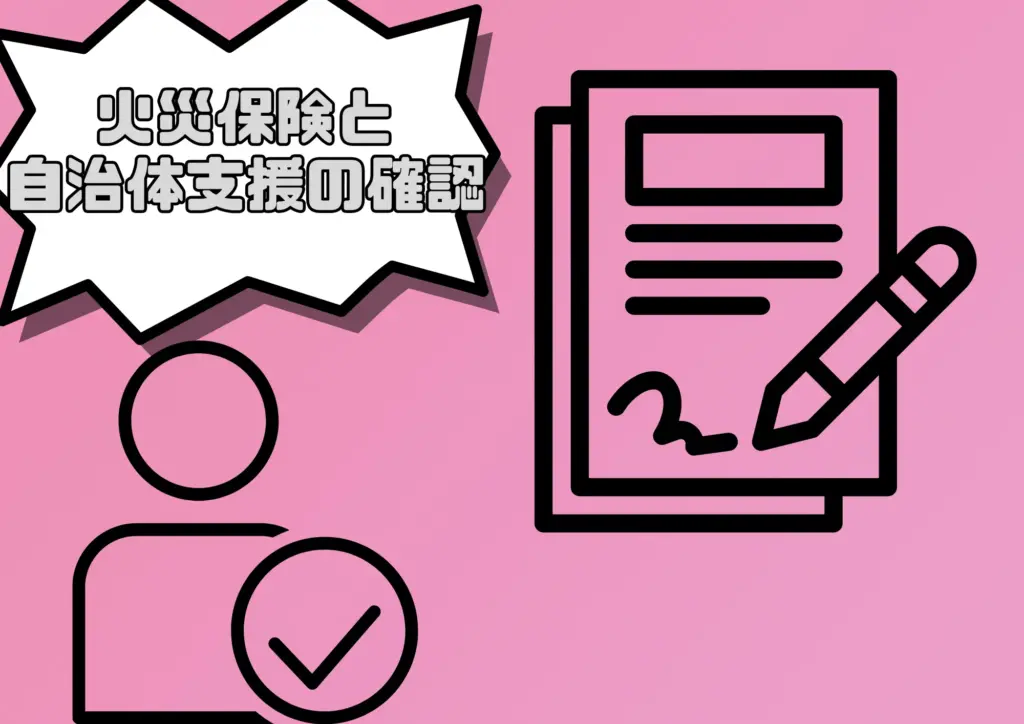
火災保険の契約内容を確認し、水害補償が含まれているかをチェックしておきましょう。
自治体によっては排水ポンプの貸出制度や応急資材の提供がありますので、事前に情報収集しておくと役立つかもしれません。
大型台風がすぐに来る前にできる冠水対策


天気予報で「非常に強い台風が接近中」と聞くと、不安になりますよね。
特に低地や川沿いの住宅など、冠水や床下浸水のリスクが高い地域にお住まいの方は、より強く心配になるでしょう。
そんなとき、台風直前にもきちんと準備することが大切です。
ここでは、大型台風が来る前にすぐ実行できる冠水対策を徹底解説。
完全に被害を防ぐことはできなくても、これからご紹介する対策を行うことで、被害を大幅に減らすことができます。
排水経路の最終チェック


先述した通り、排水経路のつまりは、冠水の原因になります。
日常的なお掃除・定期的なメンテナンスにプラスして、大型台風が来る際は前日までに家の周囲の排水溝・雨水桝・側溝を最終確認しましょう。
特に玄関前や車庫前など水が溜まりやすい箇所は念入りにチェックしてください。
もしつまりがひどい場合は、スコップやほうきで取り除き、できるだけ水の通り道を確保します。
止水板や水嚢の設置
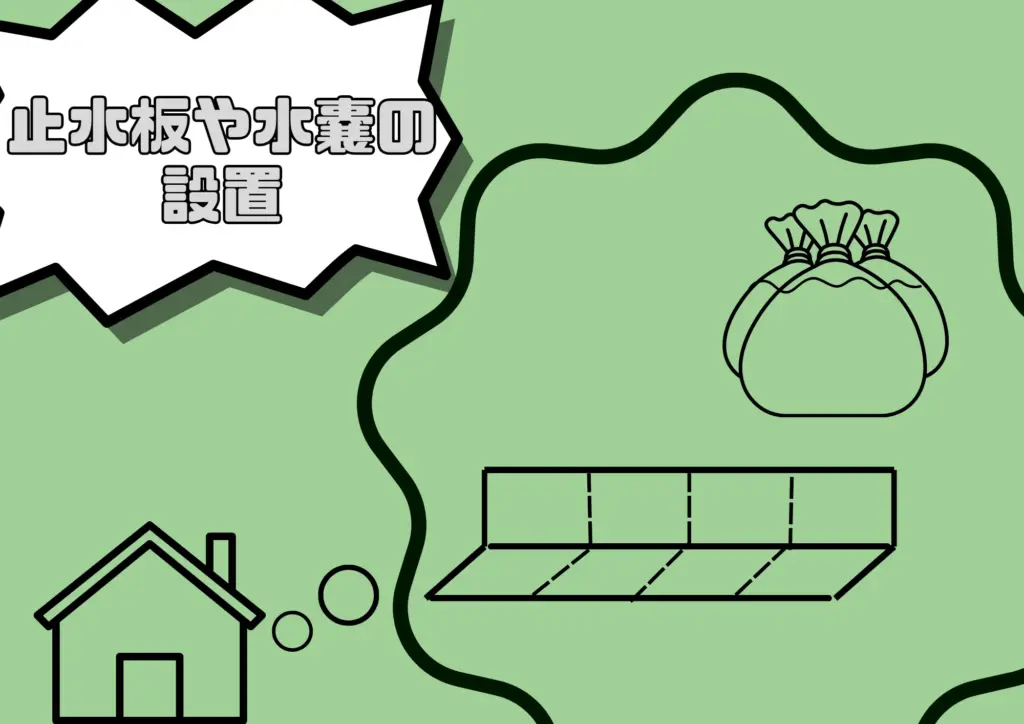
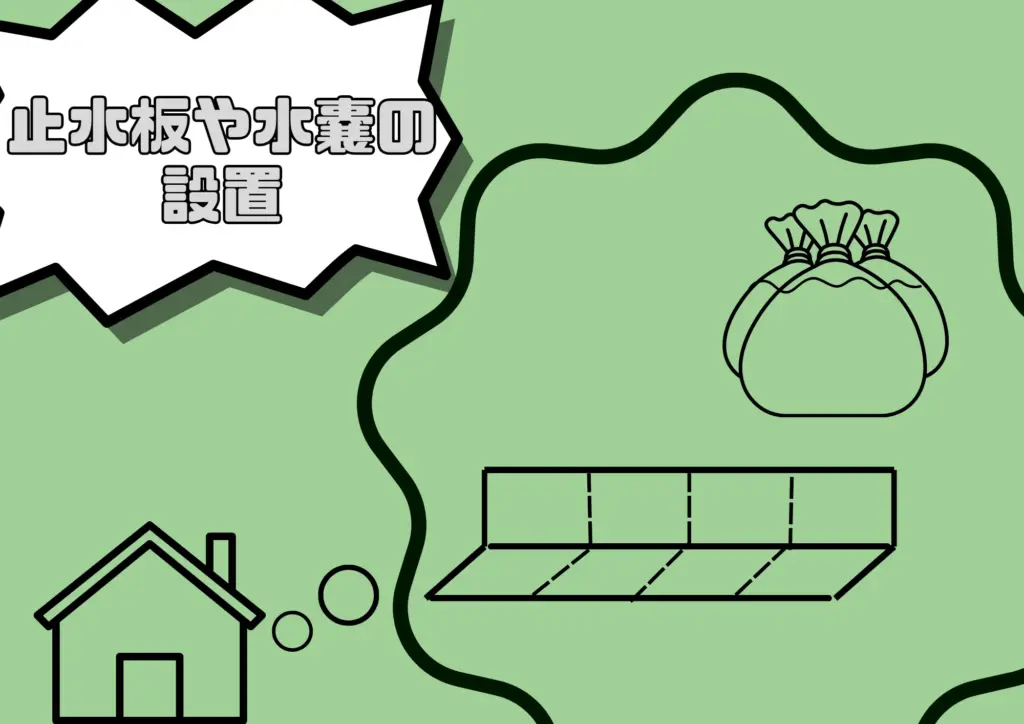
玄関やガレージの入口など、低い位置から水が入りやすい箇所には、止水板や水嚢(すいのう)を設置しましょう。
止水板はホームセンターやネットで購入でき、水嚢は自治体が配布している場合もあるので調べてみてください。
事前に購入しておいて、前もって設置する位置を想定しておくと、より安心です。
家電・貴重品の移動
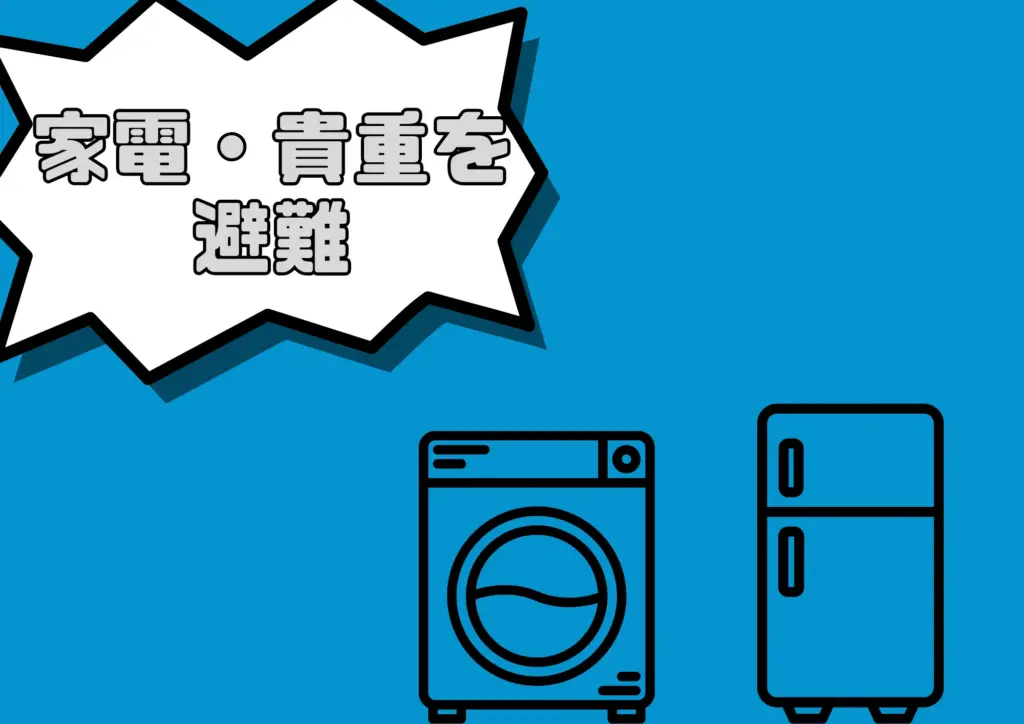
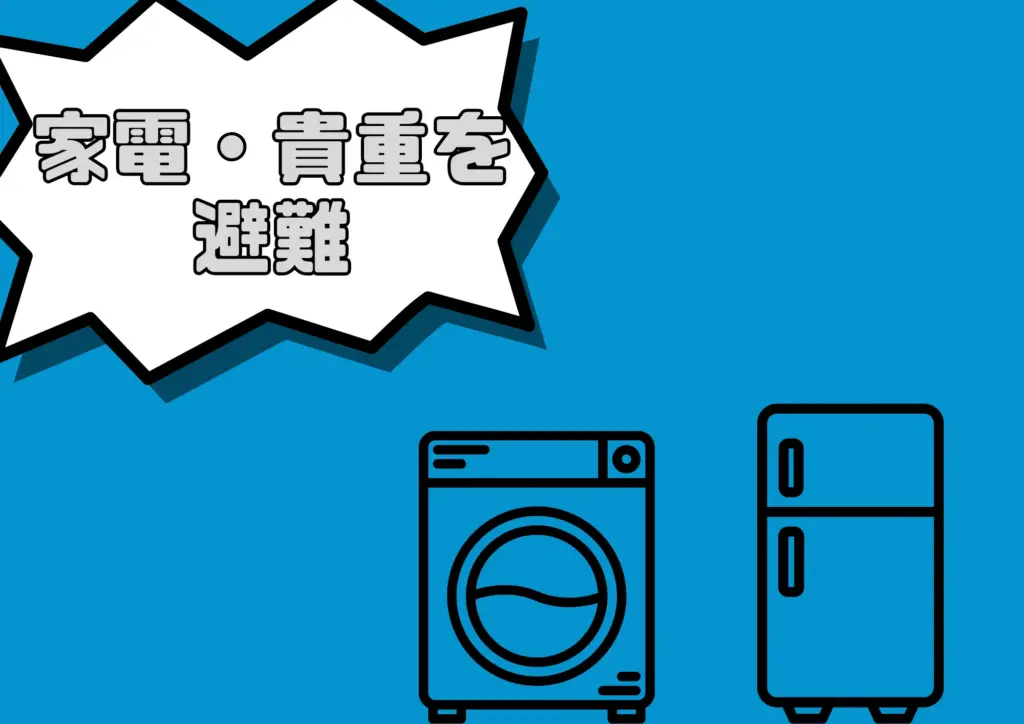
床上浸水の恐れがある場合は、家電や重要書類、写真アルバムなど大切なものを2階や高い棚に移動しておいてください。
特に冷蔵庫や洗濯機は被害額が大きくなるため、ブロックや台の上に避難させましょう。
被害が出た時に備え、家の外観や室内の様子をスマホで撮影しておくと、保険申請時の証拠になります。
車を高台へ避難
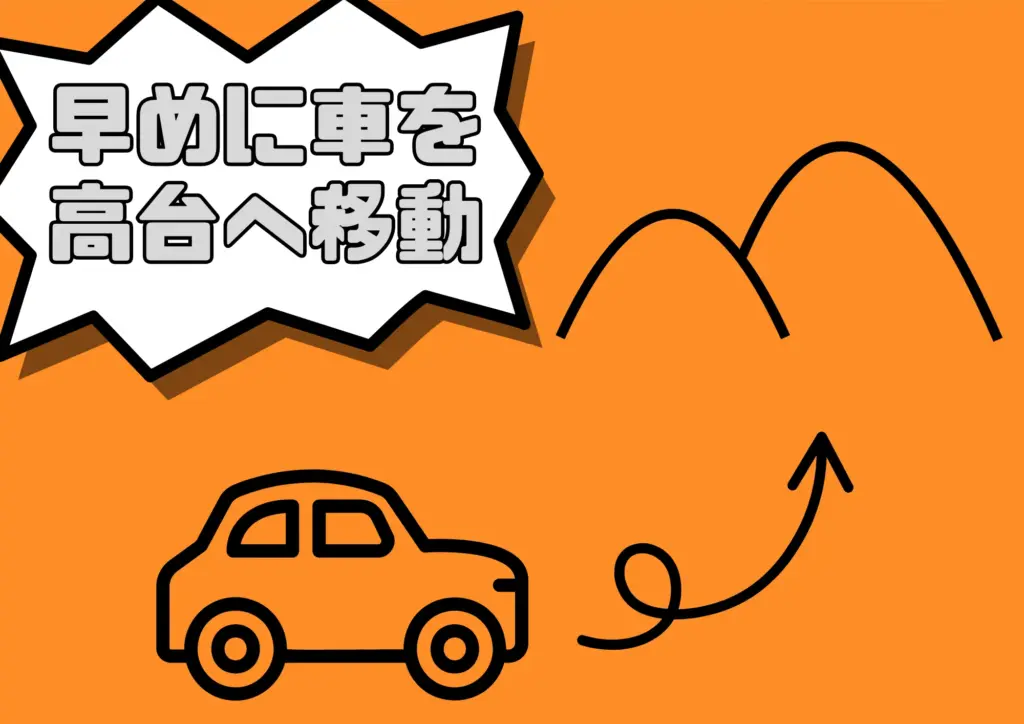
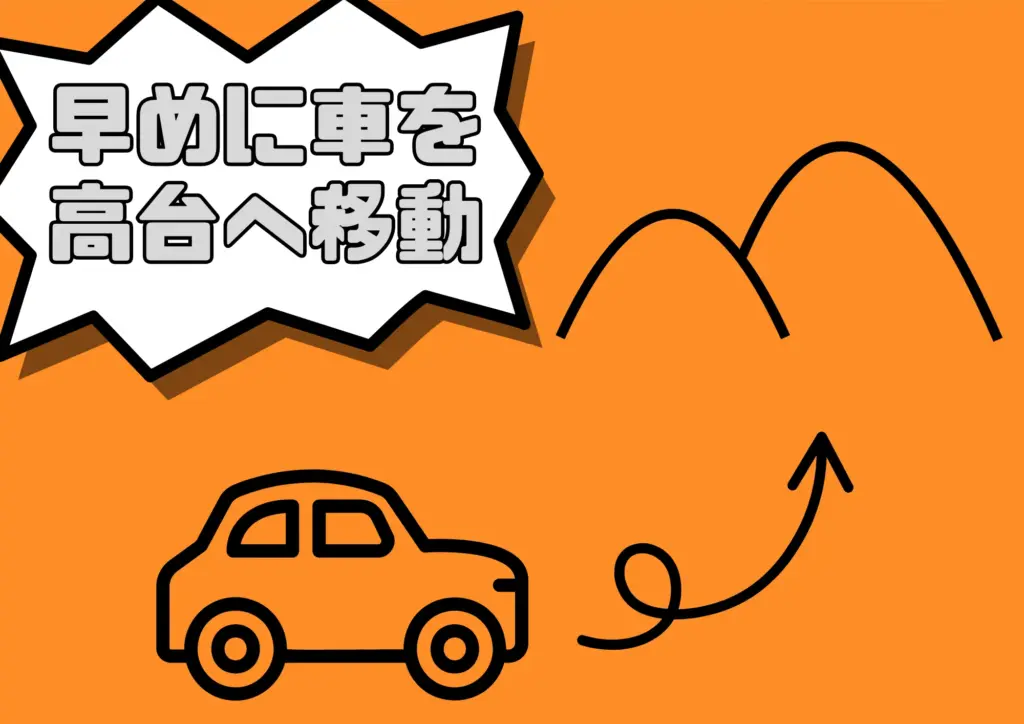
自宅前が冠水しやすい場合は、早めに車を高台や立体駐車場に移動させましょう。
移動が遅れると道路が冠水して車が動かせなくなる恐れがあるので、早め早めの行動が鉄則。
特にハイブリッド車や電気自動車は浸水に弱いためご注意ください。
ブレーカーを落とす準備
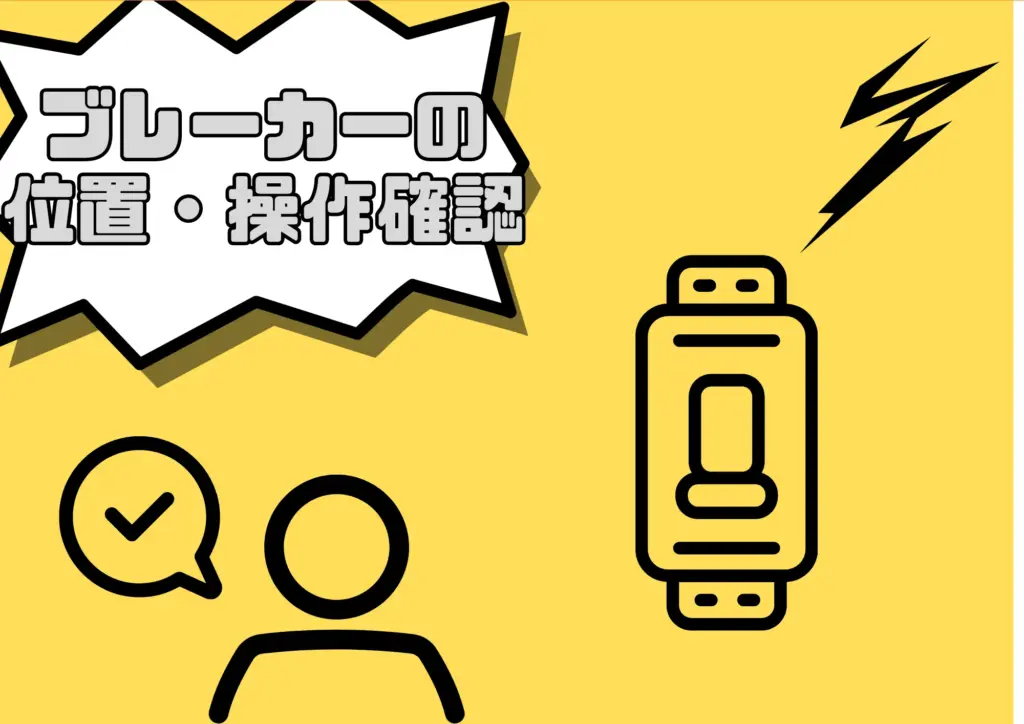
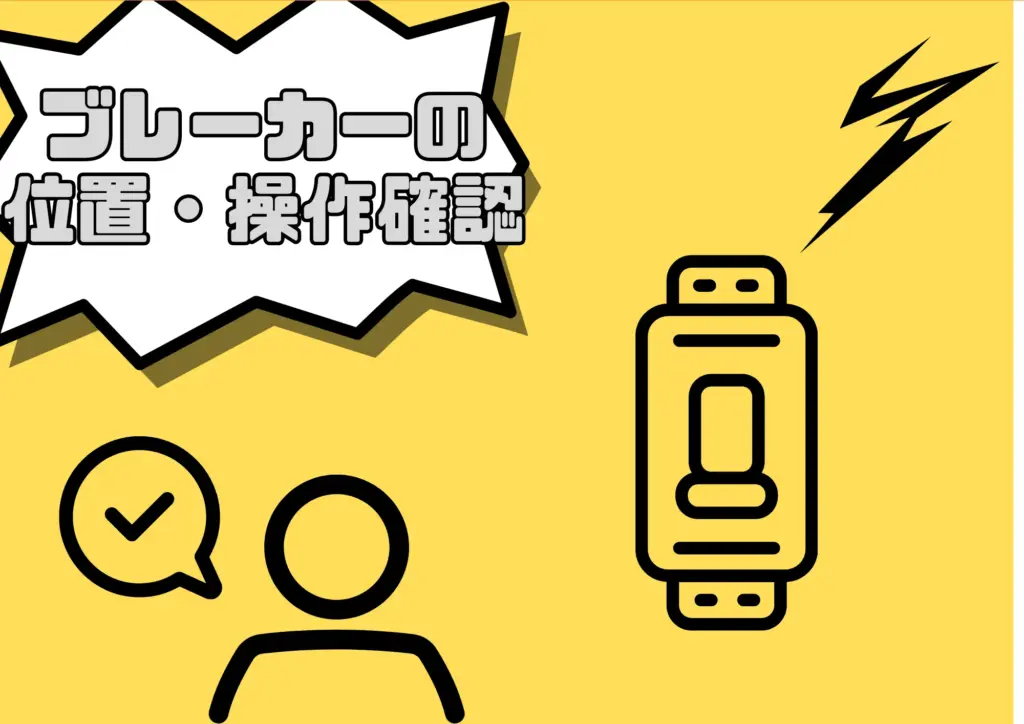
冠水して電源プラグや電化製品が濡れると、感電や漏電を起こすことがあります。
非常に危険なため、冠水が迫ってきたら感電を防ぐためブレーカーを落とすことが必須。
事前にブレーカーの位置や落とし方を家族で確認しておきましょう。停電や冠水時に慌てず安全を確保できます。
家族・近隣との連絡体制を確認


避難が必要になった場合に備えて、家族や近隣の方と連絡が取れる手段を確認してください。
避難所の場所やルートも事前に把握しておくと安心です。台風の勢力によっては早めの自主避難も視野に入れましょう。
冠水後にやってはダメなNG行動


台風や豪雨による冠水被害。水が引くと「やっと片付けられる…」と安心してしまいますが、実はここからが本当の危険の始まりです。
冠水直後の住宅には、見た目では分からないリスクが潜んでおり、誤った行動が二次被害や健康被害を招くこともあります。
ここでは、冠水後に絶対やってはいけないNG行動とその理由をご紹介します。
すぐに電気を使う
水に浸かった家電や配線は、見た目が乾いていても内部に水分が残っている可能性があります。
その状態で通電すると、感電や火災の危険があるので、すぐに電気を使うのは絶対にやめてください。
特に床下や壁の中に配線が通っている住宅は要注意。エアコンや換気扇も含まれるので、気をつけましょう。
必ず電気業者や工務店に点検してもらい、安全が確認されるまで使用しないでください。
床下や浸水部分に素手・素足で入る
冠水の水は下水や生活排水が混じっており、大腸菌やカビ胞子、化学物質などが含まれているので危険。
素手や素足で触れると、皮膚炎や感染症のリスクが高まります。復旧作業の際は、必ず長靴・手袋・マスクを着用しましょう。
濁った水や泥を放置する
「水は引いたし、片付けは明日でいいか」と思っていると、わずか1日でもカビが繁殖し、悪臭や健康被害が急速に進行します。
特に床下に泥が残ると湿気がこもり、木材の腐食やシロアリ被害が発生することも。早期の排水・泥出しが重要です。
家具や畳を室内で乾かす
浸水した家具や畳を室内で乾燥させると、湿気がこもりカビが爆発的に増えます。
必ず屋外の風通しの良い場所で乾燥させ、状態によっては処分も検討しましょう。
自己判断で修理を始める
被害状況を記録せずに修理を始めると、火災保険や自治体の支援制度が使えなくなることがあります。
修理前に、被害箇所や水位の痕跡を写真・動画で記録しておきましょう。これが後の補償手続きに欠かせない証拠になります。
台風による冠水被害に適用される補助金制度と火災保険
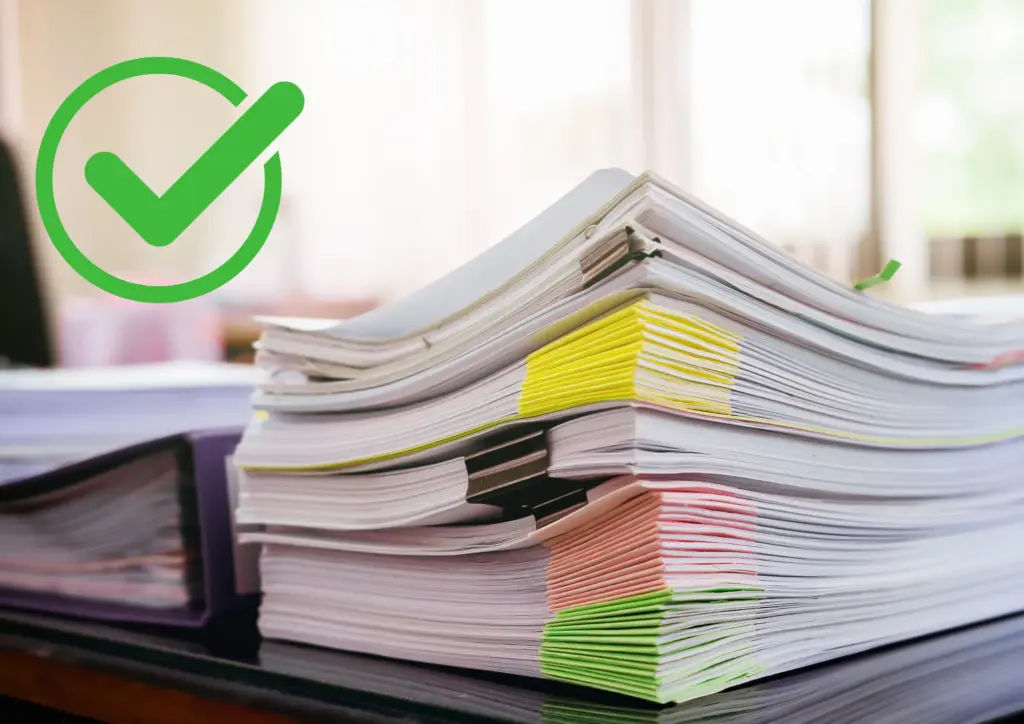
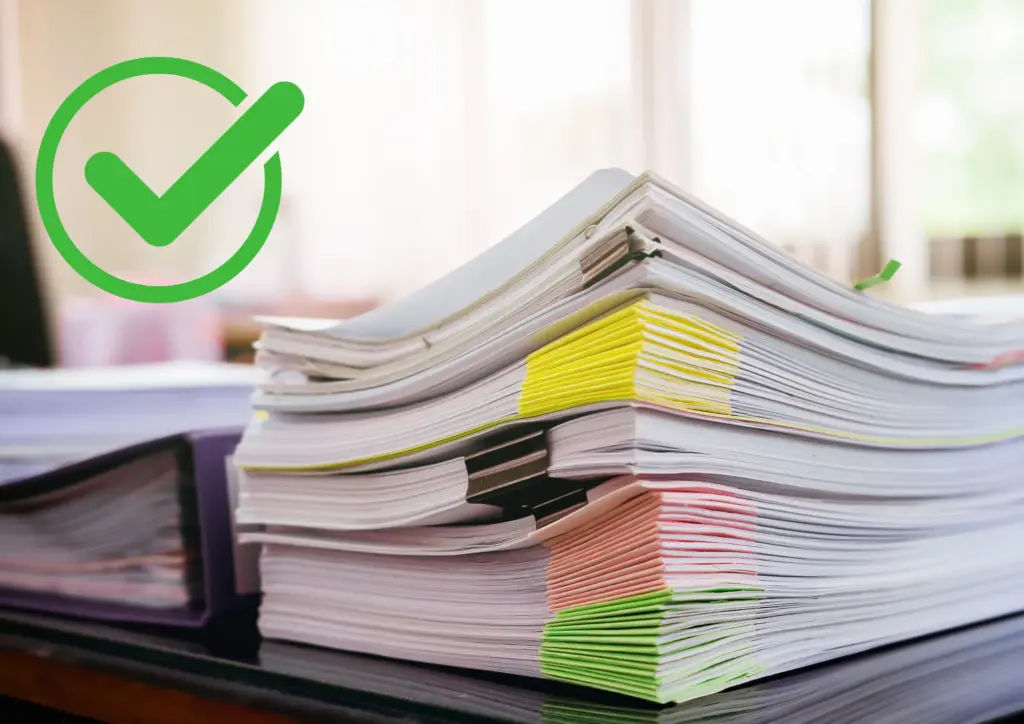
台風や豪雨による冠水被害は、住宅の床下や床上まで水が入り込み、構造や設備に大きなダメージを与えます。被害によっては、修理費用がとても高額になることも。
しかし、補助金制度や火災保険を活用すれば自己負担を大幅に減らせるかもしれません。
ここでは、補助金制度と火災保険についてわかりやすく解説します。
自治体の補助金制度
多くの自治体では、台風や豪雨などの自然災害で被災した住宅に対し、修理費の一部を支援する制度があります。お住まいの市区町村の公式ホームページなどで確認してみてください。
自治体が実施している主な制度は、下記の2つ。
- 住宅復旧支援金
全壊・半壊・床上浸水などの被害を受けた場合、修理費の一部を補助。上限額は自治体により10万〜50万円程度。 - 防災・減災工事の補助金
冠水再発防止のための止水板設置や外構排水改善工事などに適用されるケースがあります。被害後の復旧だけでなく、予防工事にも使えるのが特徴です。
補助金を受けるには、罹災証明書の取得が必須。市区町村役場に申請し、職員による現地確認を受けた後に発行されます。証明書がなければ、ほとんどの補助金や保険金が支給されません。
火災保険の水害補償
火災保険は「火事」だけでなく、契約内容によっては台風や豪雨による水害も補償対象になります。
まずは対象になる被害の例と補償の範囲をご紹介。
- 対象となる被害例
床上浸水、地盤面から45cm以上の床下浸水、雨水や河川氾濫による家財損害など。 - 補償の範囲
建物だけでなく、家具・家電などの家財も対象になる契約があります。
申請の流れ
申請の流れをわかりやすく解説します。
- 外観(浸水高さが分かるようにメジャーと一緒に撮影)
- 室内の被害箇所(家具・家電・床・壁)
- 家財は型番や状態が分かるように
「水が引く前」と「引いた後」の両方を撮ると説得力が高まります。
- 契約している火災保険の証券番号・契約内容を確認して連絡。
- 被害状況、発生日、住所を正確に伝える。
- 「水害補償」の対象かどうか、その場で確認。
- 必要書類や今後の流れを聞き、メモを残す。
- 罹災証明書(市区町村役場で申請。職員が現地確認後発行)
- 修理見積書
- 被害写真・動画
- 家財リスト(品名・型番・購入時期・おおよその金額)
- 気象庁データ(豪雨・台風の発生証明)



ROY株式会社は、提出書類準備のサポートも承っております!
お任せあれ
- 修理を始める前に、保険会社が依頼する損害鑑定人(アジャスター)による調査を受ける。
→ 修理後だと被害証拠が消え、保険金が減額される可能性あり。
- 調査結果・提出書類をもとに、保険会社が支払額を決定。
- 決定後、数週間〜1ヶ月ほどで指定口座に振込。
- 保険金を元に、修理を開始。
- 予防工事(止水板や排水改善)も合わせて検討すると再発リスクを減らせる。
火災保険の水害補償は契約内容によって大きく異なるので、詳しい条件や申請手順は事前にご確認ください。
補助金と保険の併用するなら
補助金と火災保険は基本的に併用可能ですが、補助金額が保険金に影響する場合もあリます。事前に保険会社や自治体に確認しましょう。
併用することで、修理費のほとんどをカバーできるケースもあります。
まとめ
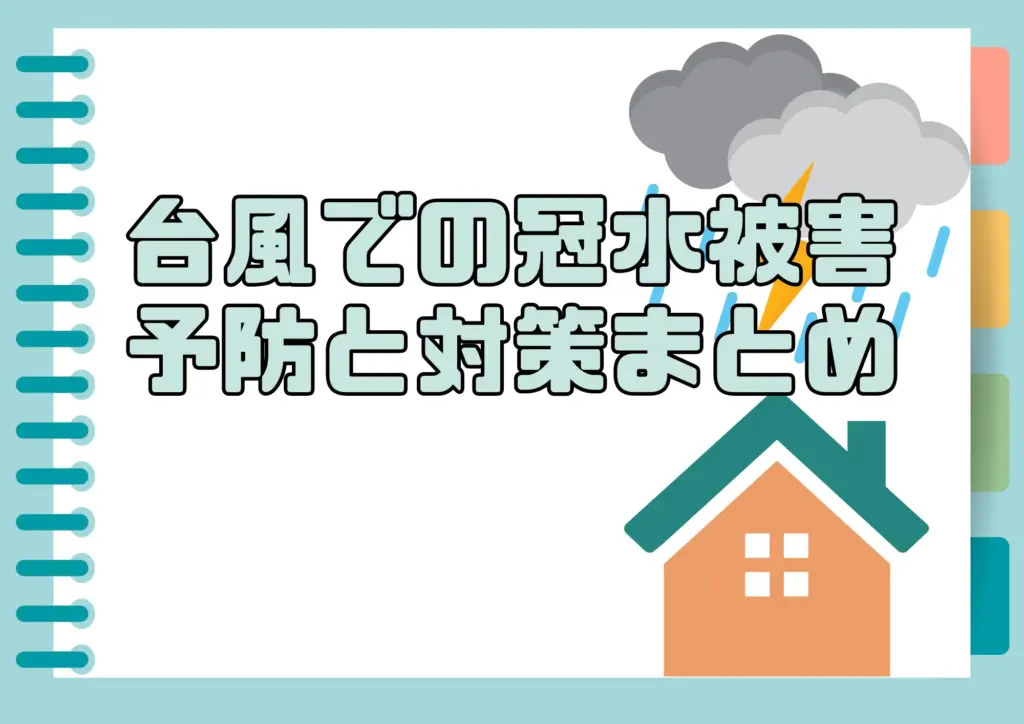
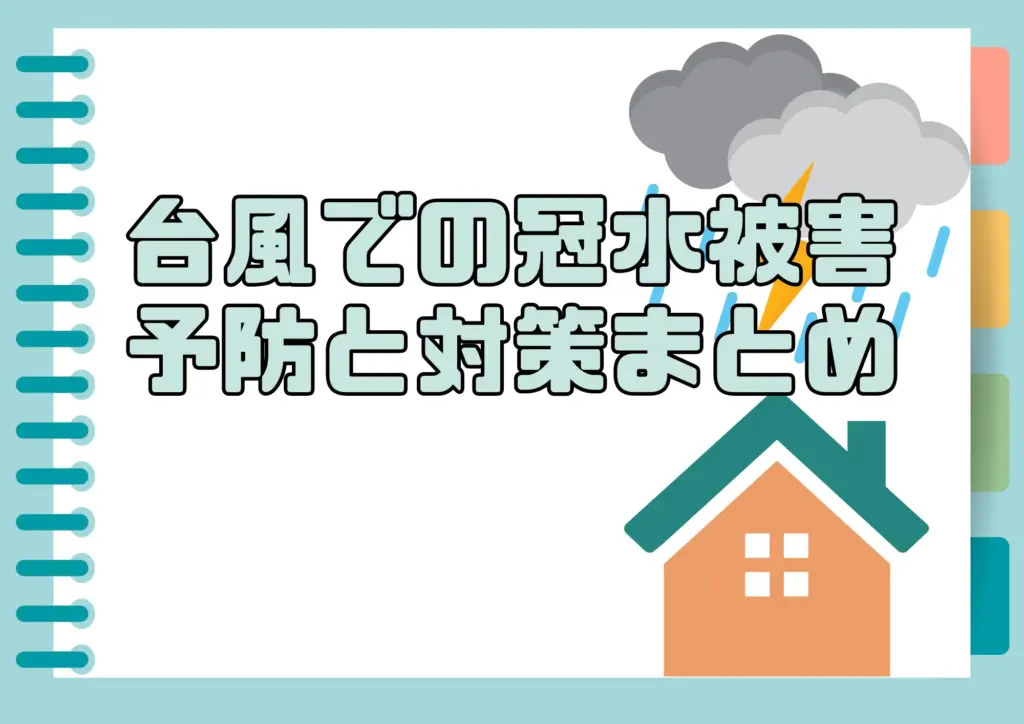
冠水は一度でも経験すると、その被害の大きさに驚きます。
そのため、できるだけ備えること、正しい知識を持って冷静に対処することがとても大切。
日々の小さな習慣と、必要に応じた工事を組み合わせれば、台風や豪雨による被害はぐっと減らせます。
被害が出る前に、是非一度ご相談ください。
ROY株式会社なら、台風での冠水被害の予防対策から修理、火災保険の書類提出のサポートまで充実。
一級建築士も在籍しており、住宅のプロの観点でみなさまの「安心できる暮らし」を全力でバックアップします。
お問い合わせ前に
ご確認ください
必ずご確認をお願いします
お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。
tel:044-328-9227
mail:info@roy-g.com
携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。
・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。
・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
プライバシーポリシー
必ずご確認をお願いします
個人情報の定義
個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。
個人情報の収集・利用
弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。
1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集
2.お問い合わせ対応各種
個人情報の第三者提供
弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。
委託先の監督
弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。
個人情報の管理
弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。
情報内容の照会、修正または削除
弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。
セキュリティーについて
弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。
Googleアナリティクスについて
当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。
個人情報に関する苦情や相談の窓口
弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。
社名:ROY株式会社
住所:〒213-0012
神奈川県川崎市
高津区坂戸3-16-1
電話番号:044-328-9227
メールアドレス:info@roy-g.com
責任者名:大石 竜次





