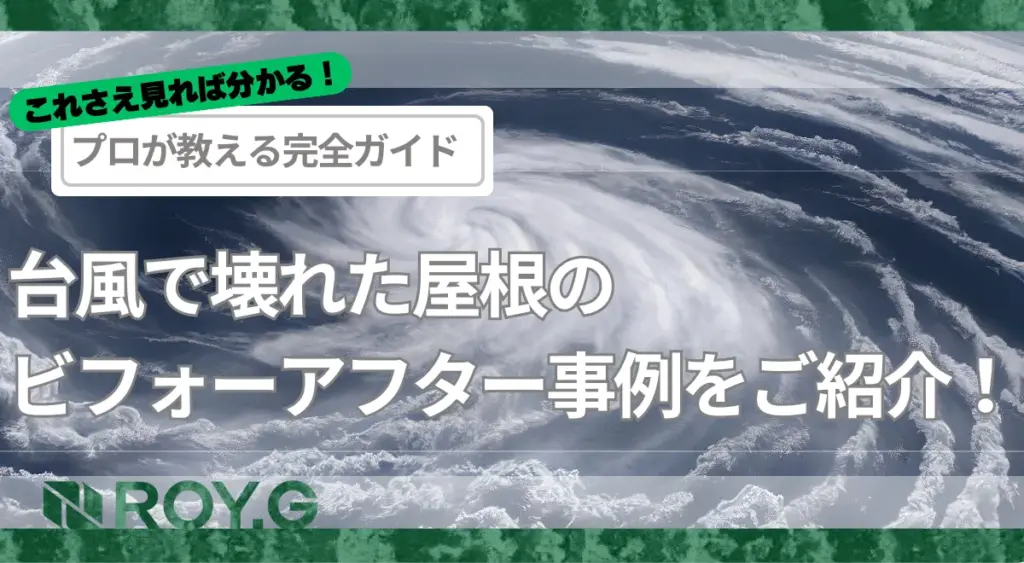
近年、日本各地を襲う台風の規模は年々激しくなっています。それにともなって住宅の屋根被害も深刻化し、特に屋根の破損や水漏れ被害は多く見られます。
この記事では、実際の屋根修理のビフォーアフター写真を交えながら、台風被害からの復旧事例をご紹介。どのような損傷が起き、どのように修復されたのかをわかりやすく解説します!
また、被害時に役立つ火災保険の活用方法や、再発防止のために重要な対策もお伝えするので、是非、ご一読ください。
台風で多い屋根の被害パターンとは?

まずは、台風が通過した後に、住宅で多く見られる屋根の被害をご紹介します。主に下記の4つのパターンが多いでしょう。

瓦のズレ・飛散
風圧により瓦が外れる。
飛ばされることで、近隣へ落下するなどの二次被害も発生するので注意が必要。

スレート(コロニアル)屋根の割れ
強風や飛来物でヒビや破片が生じ、雨漏りの原因になることも

棟板金の浮き・剥がれ
屋根の頂部にある金属板が風でめくれ、内部の防水層がむき出しになる。

屋根下地の浸水
外観は問題なさそうでも、防水層の損傷や内部腐食が進行しているケースもあり、放置すると危険。
ここからは、上記のような典型的な被害パターンの修理事例を、実際に当社が施工した写真と共にわかりやすく解説します。
どの屋根材を使ってる?
住宅で主に使われている屋根材をご紹介。自宅がどの屋根材を使っているか知ろう!
- スレート屋根(化粧スレート/カラーベスト)
セメントと繊維を圧縮して成形された薄い板板。施工費が比較的安く、デザイン性に優れているため、国内で60〜70%の使用率を誇る。耐用年数は、15年〜25年ほど。 - ガルバリウム銅板(金属屋根)
アルミと亜鉛を主成分とした合金メッキ鉄版で、金属系屋根材の主流。耐久性・防水性・軽量性に優れ、20〜30%の使用率で、年々増加傾向にある。耐用年数は、30年ほど。 - 瓦屋根(和瓦・洋瓦・セメント瓦)
粘土を焼き固めた屋根材で、伝統的な日本家屋で多く見られる。雨・風・日光に耐熱性も高く、約10〜15%の使用率。耐用年数は50年以上と非常に長い。
台風での屋根被害の修理事例をご紹介!
それでは、台風での屋根被害の修理事例を実際の写真と共にわかりやすくご紹介します。
今回、ご紹介するのは、台風によって瓦屋根への被害が生じたケース。症状としましては、「瓦のズレ・棟板金の剥がれ・屋根下地の漏水」が見られます。
経年劣化も進行しているので、屋根を全面葺き替え。お客様とご相談し、耐久性・防水性・軽量性に優れていて、長年ご安心して使用できる「ガンバリウム鋼板」を採用しました。
ビフォー|施工前の屋根の状態
施工前の状態がこちら。

鮮やかな青色の陶器瓦が使用されていますね。一見すると綺麗に見えますが、よくよく観察すると、様々な劣化や台風による被害が確認できます。
下記のような劣化や台風による被害の症状が進行していました。
- 瓦のズレや浮きが各所に見られる
- 谷部(雨水の流れる凹部分)に錆び・雨染み
- 棟板金のズレや漆喰の崩れ
- 既に一部では雨漏りが発生しており、室内天井にシミが出ている状態
築年数から考えても、屋根下地(野地板)や防水紙の劣化が進んでおり、今後のことも考えると、部分修理ではなく屋根全体の工事が必要と判断しました。
屋根下地や防水紙が劣化すると、水漏れが発生。水漏れを放置すると、住宅の基盤が劣化したり、シロアリが発生しやすくなるため、被害の拡大が予想されます。そうなると、大掛かりな工事が必要になるので、早めの修理が鉄則。
シロアリについては、下記の記事でご紹介しているので、ご参考ください。
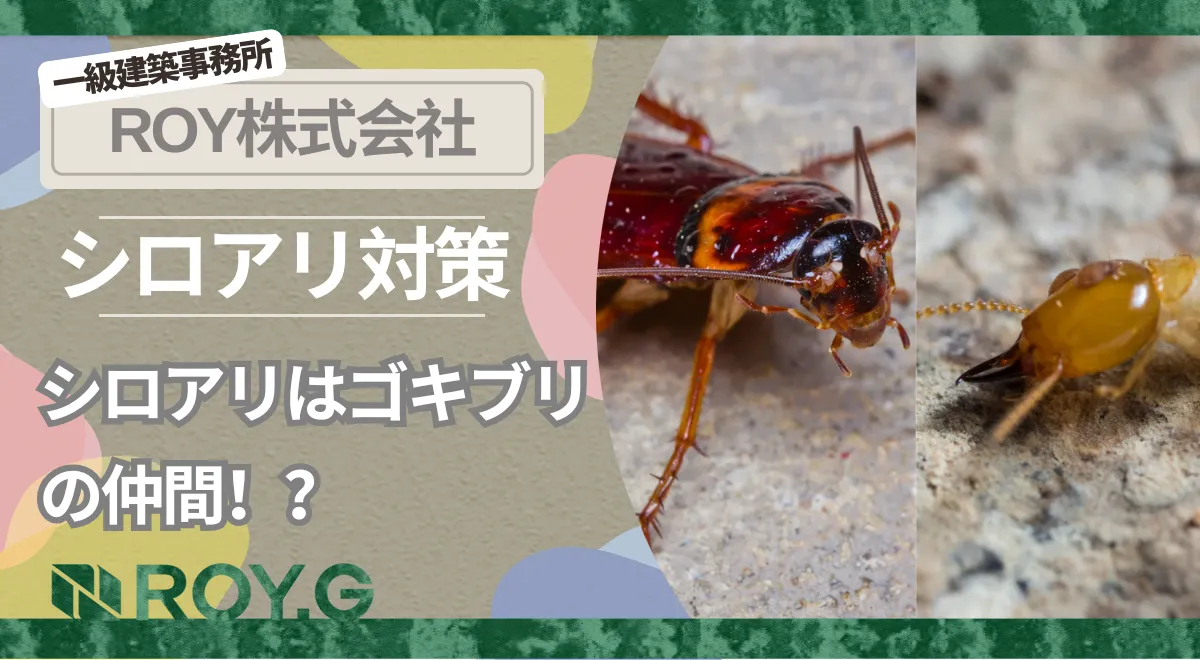
まずは既存の瓦と土葺きを丁寧に撤去します。瓦屋根はとても重いので、1軒分の撤去作業だけでもかなり体力勝負な作業。

これが瓦と土がすべて撤去された直後の様子です。下地の木材の上には、湿気によって黒ずんだ箇所も見受けられ、長年の経年劣化が明らかになりました。
土葺きってなに?
土葺き(つちぶき・どぶき)とは、瓦屋根の工法の一つ。瓦の下に土を敷き詰めて瓦を固定する方法で、湿式工法とも呼ばれる。粘土の接着力で瓦を固定するため、かつては強風や地震に強いとされて、明治時代から昭和初期まで主流だった。しかし、屋根が重くなるため、耐震性に劣るという欠点があり、現在ではあまり用いられていない。

こちらは、屋根面に垂木(たるき)を追加して補強している工程。新たな屋根材の取り付け位置を確保しつつ、荷重を分散させるための重要な作業です。
野地板を全面に敷き詰めていきます。隙間なく張ることで、屋根全体の強度と平滑性を高めます。

ここは屋根の“骨格”となる部分であり、仕上がりの精度にも直結するのでとても大切な工程。
野地板ってなに?
野地板(のじいた)とは、屋根を葺くための下地となる板のこと。「野」という字は見えないところに用いるという意味で、屋根材の瓦などの下に入っていて、屋根の上からは見ることがないことから「野」地板という字が使われている。垂木の上に張られ、屋根材や防水シートを支える役割を担う。普段は目にすることのない部分だが、屋根の耐久性や防水性を確保するために重要な役割を担っている。

これは**ルーフィング(防水シート)**を全面に敷設した状態。万が一屋根材の隙間から水が侵入しても、この防水層が住宅への水の浸入を防ぐので、非常に重要な工程です。
今回は耐久性の高い改質アスファルトルーフィングを採用。屋根の寿命を左右する要ともいえる工程です。
新たに取り付けるガルバリウム鋼板屋根材の設置をしている様子。

設置している金属屋根材の特徴をご紹介します。
- 超軽量で、なんと瓦の1/10程度の重さ
- 錆びにくく耐久性が非常に高い(20〜30年以上)
- 地震の際に屋根の荷重を軽減
- モダンでスタイリッシュな外観が魅力
また、棟部や軒先に木下地を施工して、仕上げの金属板材をしっかり固定できるように準備しました。
アフター|施工後の完成状態
こちらが施工後の完成したアフター写真。

どうでしょう?全体に張り巡らされた**ガルバリウム鋼板の立平葺き(たてひらぶき)**によって、重厚感とスタイリッシュさを兼ね備えた仕上がりに。
見た目だけでなく、耐久性や防水性、軽量性もアップ。今後もご安心して住み続けられる屋根になりました。
ビフォーとアフターで変わった点をご紹介します。
- 屋根全体に統一感があり、雨水の排水性もアップ
- 棟部分も綺麗に収まり、風圧や雨仕舞いへの対策も万全
- 旧瓦の重量が無くなったことで、構造的な負荷も大幅に軽減
屋根修理で火災保険が使えるケースとは?

台風で屋根被害に遭った場合、気になるのは修理費用ではないしょうか?被害状況によっては、なかなかな費用になることも。
しかし、台風による屋根被害の多くは、「自然災害による突発的損害」として火災保険の対象になります。
火災保険が適用される主な自然災害は下記の通り。
- 風災(台風・突風・竜巻・強風など)
- 雹災(ひょう)
- 雪災(積雪・雪崩)
台風による屋根の損傷はこの「風災」に含まれます。
ここでは、火災保険を利用するためのポイントや注意点、申請の流れをご紹介。火災保険について知って、正しい対処や手続きを行いましょう。
火災保険が適用されるポイント
台風による屋根被害が発生したときに、火災保険を利用するには、いくつかのポイントがあります。これからご紹介するポイントをきちんと抑えて、火災保険を正しく申請しましょう。
ポイントその1:自然災害による突発的な被害であること
経年劣化や施工ミスなど、人為的原因は対象外。
ポイントその2:申請期限内であること(一般的に3年以内)
台風が原因と分かっていても、申請の遅れは無効になる可能性がある。
ポイントその3:被害箇所の証拠(写真・見積・報告書)があること
自己申告ではなく、専門業者による調査が必要。客観的な証拠を提出しなければならない。
火災保険を申請する際の注意点
火災保険を申請するにあたって、いくつかの注意点があります。事前に注意点を知って、対策をしましょう。
注意点その1:経年劣化はNG!
築30年以上の瓦やスレートの“自然劣化”は保険対象外になることも。
注意点その2:申請前の修理はNG!
保険会社に連絡する前に工事を完了させると、保険が下りないことがあるので要注意!
注意点その3:実費負担が発生することもある
状況や保険会社、契約内容によって、見積額すべてが保険金でまかなえるとは限らないため、事前確認をしよう。
火災保険を申請する手順
火災保険を申請する手順をご紹介します。手順を間違ってしまうと、火災保険が降りない場合もあるので、気をつけましょう。
※保険会社や契約内容によって申請方法や条件が異なる場合があります。事前に契約している保険会社にご確認ください。
手順その1:屋根の被害確認
台風後すぐに、屋根に異常があれば写真を撮る(外観・破損部・室内雨漏りなど)
手順その2:信頼できる業者に点検を依頼
無料点検を実施している業者に調査を依頼する。
手順その3:見積書・被害報告書を作成してもらう
火災保険申請に必要な書類を業者に用意してもらおう。
手順その4:保険会社へ申請(または保険代理店経由で提出)
書類と写真を保険会社に提出する(内容により鑑定人の立ち合いが入る場合あり)
手順その5:保険金の支払い決定・入金
数日〜数週間で結果通知、入金は最短で10日ほど。
手順は上記の通り。保険申請前に施工しないことと無料点検ができる業者に依頼することが大切です。

栃ノ心
ROY株式会社は点検無料!必要書類の発行も承っているので是非ご相談ください!
修理後に再発防止のために行うと良い対策

台風は地域によっては、1年のなかでも何度も来ますよね。無事修理が完了しても、再び台風が来たときに同じ被害が起きては意味がありません。
再発防止には対策が必要です。重要になってくる再発防止の対策をご紹介しましょう。
修理前の【構造診断】
単に屋根材だけを見るのではなく、建物全体の構造状況(下地の劣化・傾き・雨漏り跡など)を確認することが重要です。
- 屋根裏の結露や腐食
- 野地板や垂木の状態
- 以前の修繕履歴 など
一級建築士や屋根診断士などの専門家による調査がベスト。
問題の“根っこ”を見落とさないことが、後悔しないリフォームへの第一歩です。
部材の選定(耐風・耐水性能の高い素材)
屋根材選びは“見た目”だけでなく、“性能”も重視すべきポイントです。
例えば、
- 台風が多い地域 → 耐風圧性能の高い固定方式
- 雨量が多い地域 → 防水性能の高いルーフィング(下葺材)
- 地震対策 → 軽量屋根材(例:ガルバリウム鋼板)
修理業者の提案力も問われる部分です。「この屋根材で本当に大丈夫なのか?」確認しましょう。
修理後の【定期点検】
リフォーム後も5年・10年と屋根は風雨にさらされ続けます。
だからこそ、以下のような定期点検が重要。
- 屋根材のズレ・浮き・めくれの確認
- 棟板金やコーキングの劣化チェック
- 雨漏りの兆候(天井裏・壁クロスの変色など)
点検頻度の目安は5年に1度程度。また、台風後に早期チェックを行っておくと間違いないでしょう。
ROY株式会社では、施工後も安心が続くよう定期点検のご案内とアフターサポートを行っています。
屋根以外のパーツのチェック(雨樋・壁・庇など)
屋根だけを修理しても、その他のパーツの劣化を放置すると、雨漏りや破損が再発する原因になります。
- 【雨樋】破損や傾き → 排水不良から外壁劣化へ
- 【外壁】ひび割れ・コーキング切れ → 水の浸入リスク
- 【庇(ひさし)】釘の緩み・雨だれ → 下部の腐食
建物は全体が連動しているため、屋根リフォーム時には付帯部も一緒に点検・補修を行うことが望ましいです。
一級建築士など構造に精通した専門家が在籍する業者なら、建物全体を考慮した施工提案が可能です。
まとめ|台風被害の屋根修理は“信頼できる業者選び”から

屋根は「家を守る最後の砦」です。台風被害を受けた際、まず大切なのは“焦らず、正確な診断と信頼できる修理業者”を選ぶこと。
本記事で紹介した事例のように、被害状況や築年数によって適した工法・材料は異なります。
写真記録・応急処置・火災保険の活用・施工実績のある業者選びが復旧成功のカギです。
台風被害の屋根修理、まずは無料点検から
私たちROY株式会社では、一級建築士の視点から屋根全体を調査し、火災保険の申請サポートまで一貫して対応いたします。
関東圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)を中心に、最短即日での現地調査も可能。
「もしかして台風で屋根が壊れたかも…」
そんなときは、無料点検も行っているROY株式会社にご相談ください。
お問い合わせ前に
ご確認ください
必ずご確認をお願いします
お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。
tel:044-328-9227
mail:info@roy-g.com
携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。
・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。
・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
プライバシーポリシー
必ずご確認をお願いします
個人情報の定義
個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。
個人情報の収集・利用
弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。
1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集
2.お問い合わせ対応各種
個人情報の第三者提供
弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。
委託先の監督
弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。
個人情報の管理
弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。
情報内容の照会、修正または削除
弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。
セキュリティーについて
弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。
Googleアナリティクスについて
当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。
個人情報に関する苦情や相談の窓口
弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。
社名:ROY株式会社
住所:〒213-0012
神奈川県川崎市
高津区坂戸3-16-1
電話番号:044-328-9227
メールアドレス:info@roy-g.com
責任者名:大石 竜次





