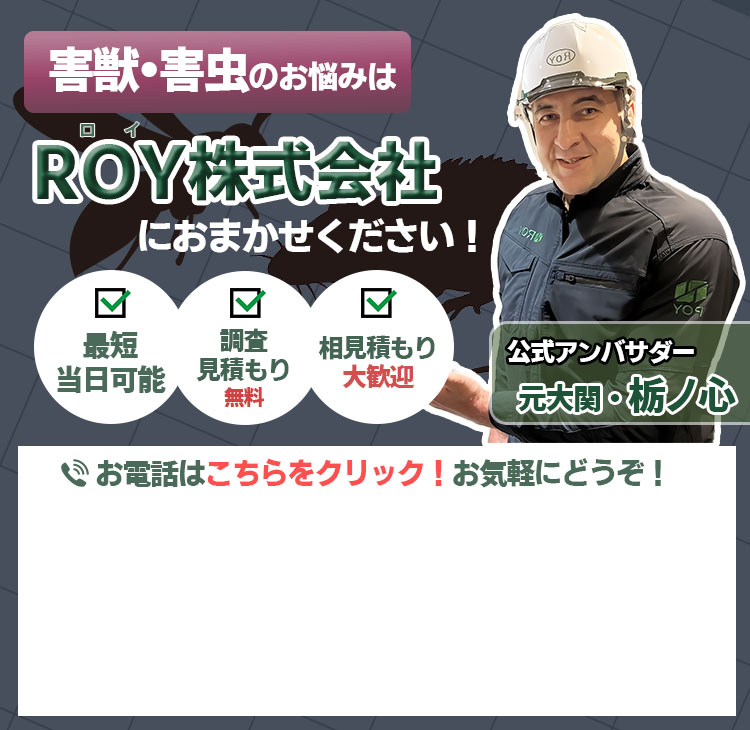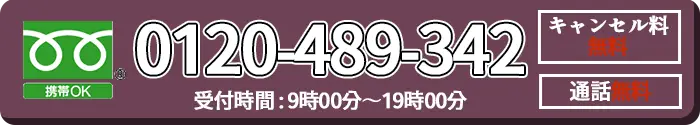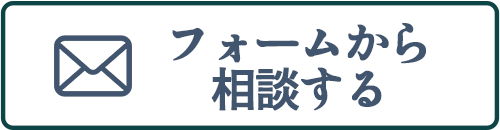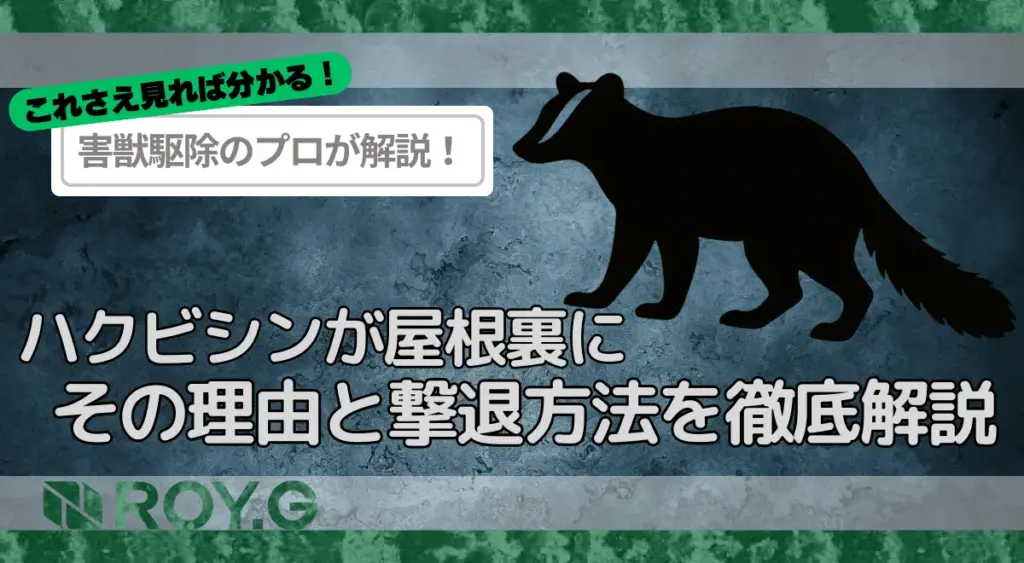
夜中に天井裏から「ドスドス」「ガサガサ」という物音がして、眠れない。天井にシミができていたり、異様なニオイが漂ってきたり…そんなとき、考えられるのがハクビシンの屋根裏侵入です。
近年、都市部でもハクビシン被害が急増しています。本記事では、「なぜハクビシンが屋根裏に住み着くのか?」「放置するとどうなるのか?」「撃退方法は?」など、屋根裏被害に悩む方向けに、わかりやすく解説します。
ハクビシンが屋根裏に住み着く理由
ハクビシンの屋根裏被害は、構造的な特徴と動物の習性が重なって発生します。
一見偶然のようでいて、実はハクビシンにとって屋根裏は「安全・快適・便利」が揃った理想的な環境です。
本章では、害獣対策の観点からも重要な「住み着く理由」を専門的にわかりやすく”5つ”に分けて解説します。
理由①:外敵から身を守れる“安全な空間”だから
野生のハクビシンは、本来は森林や山地などの木の洞・茂みをねぐらとしています。しかし都市部では、イヌ・ネコ・カラスなどの天敵や人間の活動により、安心して過ごせる場所が減少しています。
そこで選ばれるのが屋根裏。外敵が入ってこれず、静かで誰にも邪魔されない屋内の閉鎖空間は、彼らにとってまさに「シェルター」。特にメスが出産・子育てをする場所としては理想的なのです。
理由②:雨風・寒さを防げて“居心地がよい”
ハクビシンは寒さにそれほど強くありません。屋根裏は屋根材や断熱材に囲まれ、外気の影響を受けにくく、冬でも暖かいのが特徴です。
また、雨風が直接当たらないため、体温が奪われず、特に気温が下がる秋冬~早春にかけては「住み着き被害」が増加します。
理由③:夜間でも安心して活動できる“静けさ”がある
ハクビシンは夜行性の動物です。昼間は物音ひとつ立てずに寝て過ごし、夜になると活動を始めます。
日中、人の目や騒音から離れられる屋根裏は、昼夜の生活サイクルを守るのに最適な場所。人の生活動線から遠いぶん、ストレスなく休める“静かな隠れ家”になってしまうのです。
理由④:食料にアクセスしやすく“生活しやすい”
ハクビシンの食性は雑食性で非常に柔軟です。果物、野菜、昆虫、小動物、パンや菓子などの人間の残飯まで食べます。そのため、人家周辺の「家庭菜園・生ゴミ置き場・ペットフード」などは、絶好の食糧源。屋根裏に住んでいれば、家の周囲の餌場にも簡単にアクセスでき、「通う」より「住んだ方が楽」という判断をするのです。
理由⑤:登りやすく侵入しやすい“構造的な問題”がある
ハクビシンは木登りが得意で、電柱やフェンス、雨どい、隣の木などを使って簡単に屋根に上れます。そのうえ、多くの住宅は以下のような小さな隙間や老朽箇所を抱えており、そこから簡単に侵入されてしまいます。

| 侵入しやすい場所 | 状況 |
|---|---|
| 屋根瓦のズレ | 強風や老朽化でできた 5〜10cmのすき間 |
| 通気口・換気口 | 金網が破れたり、施工不良で開口部ができている |
| 軒下の隙間 | 外壁と屋根の接合部、破風板の劣化箇所など |
特に築20年以上の木造住宅は、建物の歪みや老朽化によって微細な侵入口が増えがちです。
ハクビシンが屋根裏に住み着いている兆候とは?
ハクビシン被害なは具体的な兆候があります。ハクビシンは夜行性で警戒心が強いため、姿を見せなくても行動の痕跡を残しています。以下のようなサインが複数当てはまれば、屋根裏に住み着いている可能性が高いと考えられます。
以下のようなサインが見られたら、屋根裏にハクビシンがいる可能性が高いです。
① 夜中に天井裏から物音がする

ー危険なサインー
- 天井から「ドスン」「ガサガサ」と音がする場合。
- 夜間によく音がする場合。
- 虫が増えた場合。
ハクビシンは体重が3〜5kgほどある中型獣のため、屋根裏を歩くと「ドスン」「ガサガサ」と比較的大きな音を立てます。特に夜間(21時〜明け方)に足音や物を引きずるような音が聞こえる場合、ハクビシンの可能性があります。
② 天井や壁にシミ・異臭がある

ー危険なサインー
- 天井にシミがある場合。
- 悪臭が続いている場合。
- 軋む音がする場合。
屋根裏にフンや尿をされると、天井にシミができたり、カビのような異臭が漂ったりします。ハクビシンは同じ場所で排泄する「溜めフン」の習性があるため、被害が進むと天井板の腐食や落下につながることも。
③ 家の周辺や屋根裏にフンがある

ー見分けるポイントー
- 長さ4〜5cmほどの細長い形状。
- 果物のタネなどが混じっていることがある。
ハクビシンのフンは長さ4〜5cmほどの細長い形状で、果物のタネなどが混じっていることがあります。天井裏や床下に同じ場所にまとまってある場合、他の動物(ネズミ・アライグマ)と見分ける重要な手がかりになります。
④ 鳴き声や唸り声が聞こえる

ー危険なサインー
- 「キュッキュッ」「シャーッ」と聞こえる。
- 深夜や明け方によく聞こえる場合。
出産・子育て中のメスや、複数頭が同居している場合には、「キュッキュッ」「シャーッ」といった鳴き声や唸り声が聞こえることもあります。とくに深夜や明け方に鳴く場合が多く、繁殖している可能性も。
⑤ 屋根や壁に足跡・爪痕がある

ー危険なサインー
- 外壁に引っかき傷や足跡がある。
- 換気口のネットが破れている、屋根瓦がずれている
- 前後で足の大きさが異なる場合。
ハクビシンは雨どい・ベランダ・電柱などを伝って屋根まで登ることができます。その際に外壁に引っかき傷や足跡、毛などの痕跡が残る場合があります。また、換気口のネットが破れている、屋根瓦がずれているといった侵入痕が見つかるケースもあります。
⑥ ペットの様子がおかしい

ー危険なサインー
- ペットがよく吠えるようになった場合。
- マーキングを行うようになった場合。
犬や猫が屋根裏や天井方向に向かって吠えたり、警戒する素振りを見せる場合も要注意。人間には聞こえない小さな音やにおいに反応している可能性があります
⑦ 家の周囲の果樹・野菜が荒らされている

ー危険なサインー
- 庭や畑の果物が荒らされている場合。
- 外のペットフードが荒らされている。
- 足跡がある場合。
ハクビシンは果物や野菜が大好物。庭の柿やブドウ、トマトが一部だけ食い荒らされていたり、ペットフードが減っていたりする場合は、夜中にハクビシンが出入りしている証拠かもしれません。
兆候が見られたら、早めの対処がカギ!
これらの兆候が”1つ”でも当てはまるなら、ハクビシンがすでに屋根裏に住み着いている可能性が高いです。被害は時間とともに進行し、健康被害や住宅破損につながる恐れもあるため、早期の確認と対策が非常に重要です。
今すぐ調べたいお客さまはお気軽にお問い合わせください。
次の章では、ハクビシンの侵入経路と効果的な撃退方法について詳しく解説します。
ハクビシンが屋根裏に侵入する主な経路とは?
ハクビシンは非常に身軽で木登りも得意な害獣です。電柱や雨どい、フェンス、庭木などを使って軽々と屋根まで登り、わずか5〜10cmほどの隙間からでも屋根裏に侵入してしまいます。
ここでは、特に注意すべきハクビシンの主な侵入経路5選を紹介します。
① 屋根瓦のズレ・破損箇所
瓦屋根やスレート屋根などで、台風や経年劣化でズレた部分があると、そこからハクビシンが侵入します。
とくに屋根と外壁の取り合い部分(ケラバや破風)は構造的に隙間が生まれやすく、狙われやすいポイントです。

ーチェックポイントー
- 屋根の角
- 棟瓦
- 屋根端のズレや隙間
② 換気口・通気口・軒天の開口部
ハクビシンは、通風のために設けられた小さな換気口からも侵入できます。金網や防虫ネットが破れたり、プラスチック製部材が劣化して割れたりしていると、その部分が“入り口”になってしまいます。

ーチェックポイントー
- 床下換気口
- 小屋裏換気口
- 軒天の通気穴
- 給気口
③ 雨どい・ベランダ・電線を伝って屋根へ
ハクビシンは非常にバランス感覚がよく、細い雨どいや電線の上も器用に移動します。
近くに庭木・物置・ブロック塀・エアコン室外機などがあると、それを足場にして登ってくるため要注意です。

ーチェックポイントー
- 屋根まで続く構造物
(雨どい・樋・壁沿いの配線など)
④ 壁と屋根の接合部(破風・鼻隠し付近)
屋根と壁の接合部は、構造的に隙間ができやすく、建物のゆがみや劣化で数センチの開口部が生じていることもあります。
とくに破風板の裏側、鼻隠しと屋根材の隙間は、見落としやすい侵入口です。

ーチェックポイントー
- 外壁から屋根が突き出す部分
- 目視で隙間が見えるか確認
⑤ 軒下や床下の通気口・老朽箇所
ハクビシンは屋根裏だけでなく、床下に潜ってから垂直の壁内を登って屋根裏へ到達することもあります。とくに古い木造住宅では、床下の通気口や基礎の欠損部が狙われやすいです。

ーチェックポイントー
- 基礎の通気口の金網破れ
- 床下の穴
- 外壁の剥離
ハクビシンの屋根裏被害:放置するとどうなる?
ハクビシンが屋根裏に住み着いたまま放置していると、家と健康の両方に深刻な被害が出てしまう可能性があります。次のようなトラブルが起こる前に、早めの対処が重要です。
1. フン尿による悪臭・天井シミ
天井裏が溜めフンによりトイレ状態になり、悪臭・シミ・腐食が進行します。

放置すると修繕費がかさむ恐れもあります。早めに点検を行いましょう!
2. ノミ・ダニ・病原菌の繁殖
ノミ・ダニ・ウイルスが繁殖し、アレルギーや感染症の原因になります。



小さなお子さまやペットのいるご家庭は特に要注意です!
3. 騒音によるストレス・睡眠障害
夜行性のため、夜中に活動音が続き睡眠障害や精神的ストレスに繋がります。



眠れない夜が続く前に、原因を突き止めましょう!
4. 天井崩落・火災リスク
配線をかじったり断熱材を荒らして、火災や天井崩落の危険があります。



“ただの害獣”と油断せず、被害が広がる前にご相談を!
ハクビシンの撃退方法
屋根裏に住み着いたハクビシンを追い出すには、「居心地を悪くして出て行ってもらう → もう入れないようにする」ことが大切です。以下のステップに沿って対応してみましょう。
① 忌避剤を使って追い出す
まずは、市販のハクビシン用忌避剤(スプレータイプや燻煙タイプ)を使って、屋根裏から追い出しましょう。
強いニオイや煙で一時的に退避させることができます。


⚠️ ただ追い出すだけでは不十分です。再侵入を防ぐ対策が必ず必要です。
② 音・光・振動で“居心地を悪くする”
ハクビシンは静かで暗い場所を好みます。そこで、以下のような方法で環境をわざと悪くすると、自然と出て行ってくれることがあります。
・屋根裏でラジオを流し続ける
・常夜灯などで明るく照らす
・超音波装置(人感センサー付き)を設置する
💡「ここにいたくない」と感じさせることがポイントです。
③ 侵入口を見つけてしっかり封鎖する
ハクビシンを追い出した後は、出入り口を必ず塞ぎましょう。
1ヶ所でも開いていると、再び侵入されてしまいます。
ー封鎖に使えるものー
・ステンレス製の金網や鉄板
・パンチングメタル
・隙間にはコーキング材を使用


⚠️追い出す前に封鎖してしまうと、中で暴れたり別の穴をこじ開ける恐れがあります。順番に注意しましょう。
④ フンの清掃と消毒も忘れずに
ハクビシンのフンや尿には、病原菌や寄生虫(ノミ・ダニ)が潜んでいることがあります。掃除をする際は、次のような感染予防対策を必ず行ってください。
・マスク・ゴム手袋・使い捨て防護服を着用
・消毒用エタノールや塩素系洗剤で清掃
・廃棄物は袋に密封し、適切に処理






💡衛生面が心配な方は、専門業者に任せるのが安全で確実です。
ハクビシン駆除には法律の壁がある!?個人でできる限界とは
ハクビシンは鳥獣保護管理法により勝手に捕獲・殺処分できません。
| 内容 | 詳細 |
| 捕獲には許可が必要 | 市区町村から「有害鳥獣捕獲許可」を得なければならない |
| ワナの設置も制限あり | 許可なしでの箱ワナ・くくりワナ設置は違法 |
| 無許可捕獲の罰則 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象 |
つまり、ご自身で捕まえようとするのはとても危険なので、無理をせず専門の業者に相談するのが安心です。
【プロに依頼すべき理由】害獣対策は専門業者が確実!
✅ 原因調査から再発防止まで一括対応
侵入経路の特定、追い出し、封鎖、清掃・消毒まで、一連の害獣対策をワンストップで実施。
✅ 安全な手順と適法な駆除方法
法律に準拠した方法で対応するため、トラブルなく安心して任せられる。
✅ 再侵入を防ぐ建築的対策も可能
ROY株式会社のように一級建築士監修の施工会社であれば、構造面からの防除対策も万全です。
まとめ|「もしかして…?」と思ったら、早めの対策を
記事を読んで「おかしいな」と感じたら、ハクビシンが屋根裏に潜んでいる可能性があります。
放置すると、住宅の傷みや悪臭、健康被害のリスクも。
そんなときは、害獣対策のプロ・ROY株式会社にご相談ください。
ハクビシンの屋根裏被害でお困りならROY株式会社へ!
⭐️一級建築士監修で屋根裏の構造から侵入経路を完全封鎖
⭐️ 害獣対策の専門チームがフン清掃・消毒も安全に対応
⭐️LINEやフォームで簡単相談
⭐️ 無料現地調査・即日対応エリアあり!
お問い合わせ前に
ご確認ください
必ずご確認をお願いします
お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。
tel:044-328-9227
mail:info@roy-g.com
携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。
・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。
・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
プライバシーポリシー
必ずご確認をお願いします
個人情報の定義
個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。
個人情報の収集・利用
弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。
1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集
2.お問い合わせ対応各種
個人情報の第三者提供
弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。
委託先の監督
弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。
個人情報の管理
弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。
情報内容の照会、修正または削除
弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。
セキュリティーについて
弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。
Googleアナリティクスについて
当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。
個人情報に関する苦情や相談の窓口
弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。
社名:ROY株式会社
住所:〒213-0012
神奈川県川崎市
高津区坂戸3-16-1
電話番号:044-328-9227
メールアドレス:info@roy-g.com
責任者名:大石 竜次